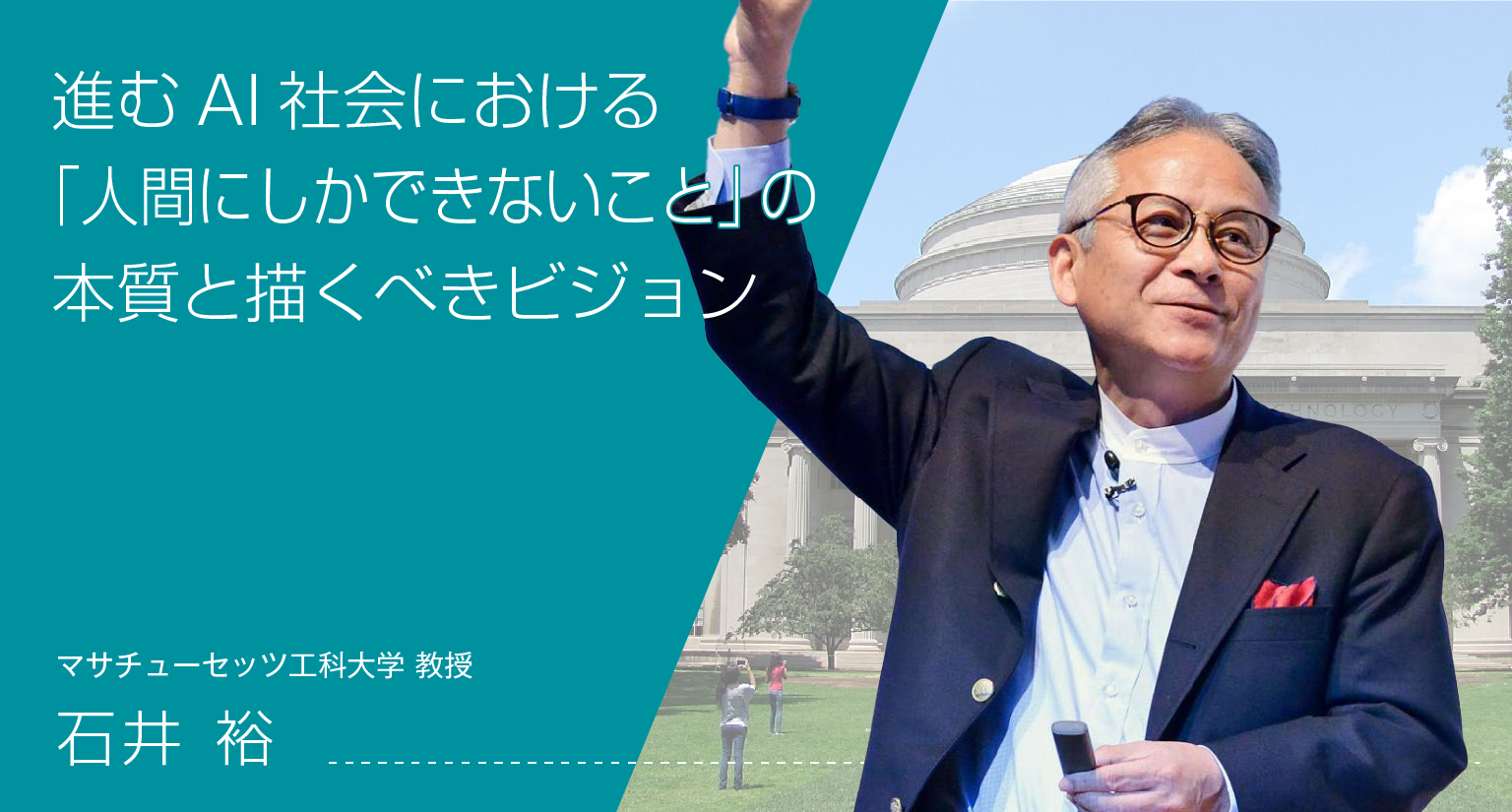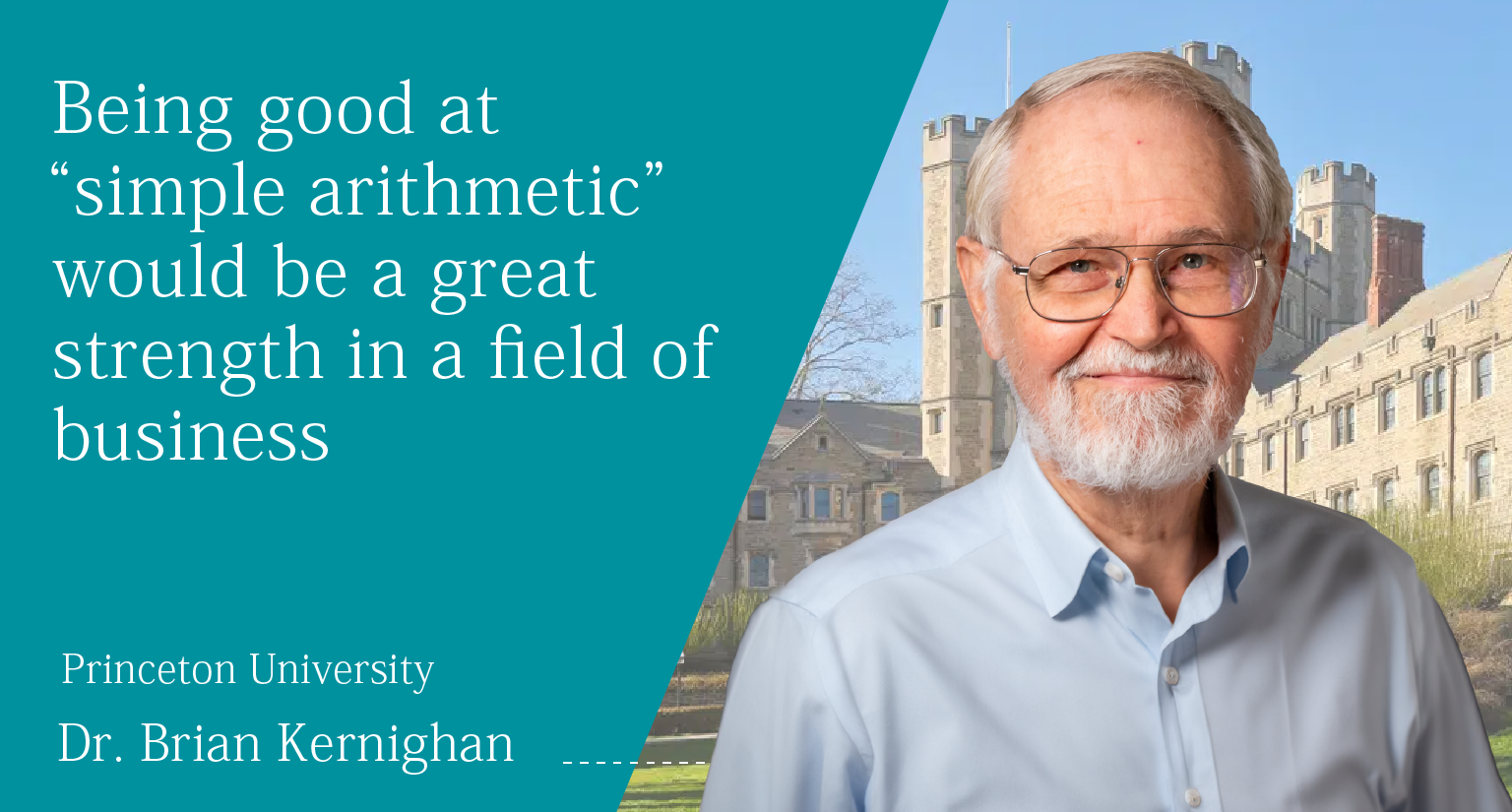ChatGPTの登場で、AI社会はますます私たちの身近なものになりつつあります。
しかし、AIの発達によって生活が便利になっていく一方で、「今の仕事はAIに取って代わられるのでは?」「人間にしかできないことを見つけるには、どうすれば良いのだろう」と悩むことも増えているのではないでしょうか。
そこで今回は、マサチューセッツ工科大学 メディアラボ副所長の石井裕先生に、人間にしかできないことの本質と、そこから描くべきビジョンについてお話を伺いました。
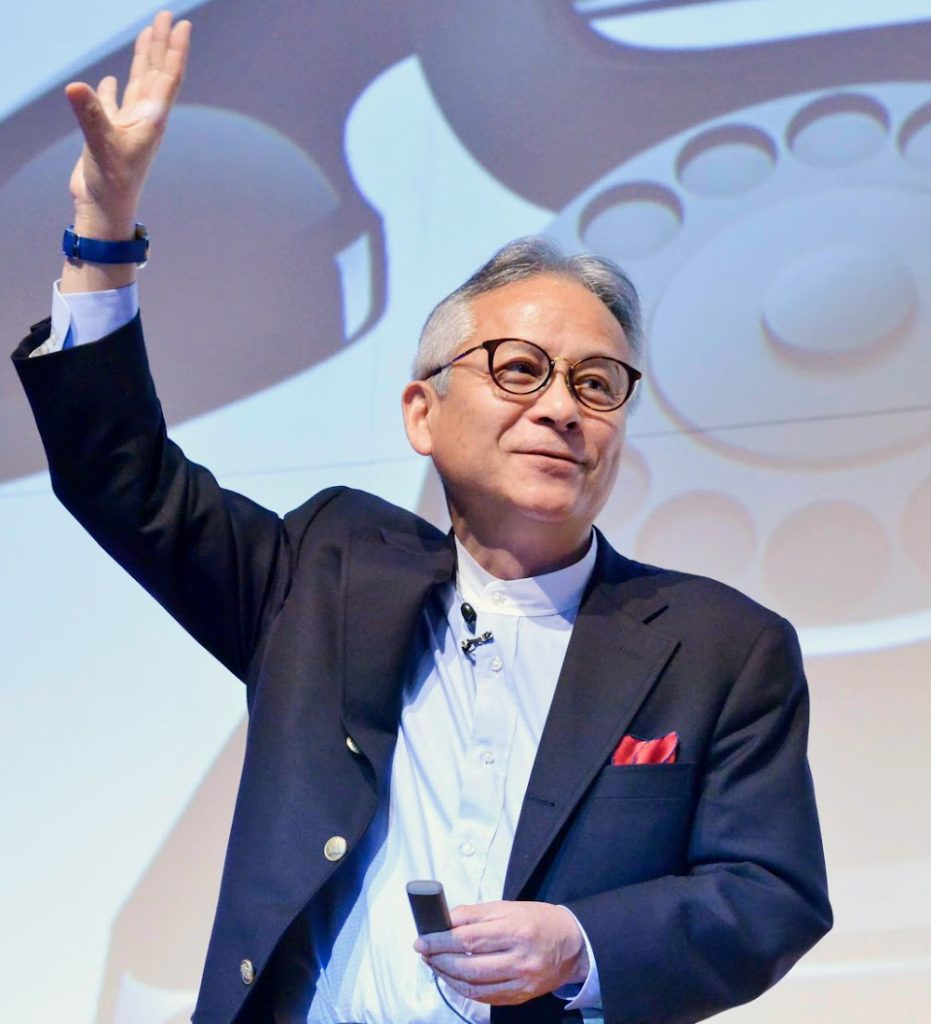
取材にご協力頂いた方
マサチューセッツ工科大学(MIT) 教授
メディアラボ 副所長
石井 裕(いしい ひろし)
1956年東京生まれ。1978年に北海道大学工学部卒業、1980年に同大学院情報工学専攻修士課程修了、日本電信電話公社 (現NTT)入社。NTT 研究所にて、ヒューマンインターフェースとリモートコラボレーション支援技術の研究に従事。1992年に北大から博士号取得。1995年からMITメディアラボにおいて直接操作・感知可能なタンジブルユーザインタフェースの研究「タンジブル・ビッツ」を進める。現在MITメディアラボ副所長、タンジブルメディアグループ・ディレクター、工学博士。2001年にMITからテニュア(終身在職権)を授与され、2006年にACM SIGCHIよりCHI Academyを受賞。2019 年には、ACM SIGCHI Life Time Research Award (生涯研究賞)を受賞。2022年に ACM Fellow に選ばれる。
「独創・協創・競創」こそが「人間にしかできないこと」
佐藤:最近はChatGPTの登場もあり、ますます人間の仕事がなくなっていくのでは、と不安を抱く声も強くなってきています。こうした状況を踏まえて、従来の発想では思いつかないような画期的な発明を次々と行っている石井先生にお聞きしたいのですが、人間にしかできないこととはどのようなものが考えられるのでしょうか?
石井先生:人間にしかできないことの本質とは何か。その答えは「独創・協創・競創」です。これらは我々が最も重要視しているもので、AIにはできない、まさしく人間にしかできないことです。言い換えれば人間が人間であるためには、「独創・協創・競創」を磨き切ることが大切だと考えています。
1つ目の独創とは、言葉の通りオリジナルなアイデアを生み出すことで、もうすでに誰かがやっていたような場合は独創にはなりません。それでは単なる二番煎じでしかないわけです。自分一人で観測できる、あらゆる現象に対して「なぜ」と問う視座を持って徹底的に検討し尽くすことで、独創性のあるアイデアが生まれます。
2つ目の協創は、他者と協力すること。独創は非常に重要なステップですが、一人の力だけでは全てのアイデアを高度化することはできません。だからこそ、ビジョンに共鳴できる少数精鋭のチームで独創を共有することが大切です。
そして3つ目の競創はコンペティション、すなわちライバルと競い合うことを意味します。世界中のライバルと最前線で競い合い、度肝を抜いてやろうという思いと、追い抜かれるかもしれないという恐怖の中で、アイデアは連続飛躍していくんです。
佐藤:「独創・協創・競創」という3つのステップを経ることで、アイデアがより高い次元、人間にしかできないレベルへと昇華されるのですね。
石井先生:そうです。AIの発達によって人間の仕事がなくなるのでは、という疑問の本質を捉えるには、まずAIがどういったものかを理解する必要があります。マシンがどういう機能限界を持っていて、AIがどうやって動いているのかを科学的・技術的に理解しているという前提がなければ、おそらくかなりの議論は空論になると思います。例えば、最近話題になっているChatGPTにしても、ランゲージモデルをどうやってラーニングしているのかという仕組みを知ることが第一歩です。
AIはすでにある情報を参照して、AといえばB、というパターンがあれば学習できます。ですが、今まで誰も考えたことがない、全く新しいものを生み出そうとするならばどうでしょう。そうした状況下では多くの場合、事前に学べる材料などありませんから、そこでAIが新しいものが生み出せるかという問いに対しては、自ずと答えが導き出されます。本当にオリジナルな、新しい地平を切り拓いていくようなコンセプト・ビジョン・技術なら、マシンは追いつきようがないんです。
佐藤:新しい地平を、となるとやはりクリエイティブな仕事が思い浮かびますね。
石井先生:そうですね。クリエイティブな要素がない仕事は、AIでも比較的簡単にできます。たくさんのデータがあって、構造的な仕事であればAIで代替がきくでしょう。でも今やっているインタビューのように、エッセンスを抽出してナラティブにし、幅広い人に伝わる形にするような作業は事前に大量の資料の読み込みが必要だし、自分自身の論理も鍛えなければいけない。こういう仕事はマシンには当分できないと思います。
もっとも、打ち出した新しいビジョンが成功して10年以上経ち、みんなが同じことをやり始めて論文や映像でデータが山ほど蓄積されていけば、それを学ぶことでAIも同じことができるようにはなるでしょう。世の中の素晴らしいコピーライターのノウハウがセミナーでものすごい数の人に共有され、そして優秀なコピーライターが増え、中でも何らかの賞を取った優秀なライターのデータが蓄積されていけば、マシンの方が優れたコピーライティングができる時代もくるかもしれません。
しかし、それではマシンのやっていることは単なる後追いです。大切なのは、AIから逃げ切れるだけの独創力を持って、協創と競創をし続けることなんです。1人ではできないことでも協創すれば実現できるし、競創することによってモチベーションが高まります。そうやって未来を切り拓き続けることによって、ランゲージモデルの学習では絶対に追いつけない、まだデータが存在しない世界へと進んでいくことができます。なので、これは追いつかれるか逃げ切れるかという、人間とマシンとの競創なんです。
目の前に広がるあらゆる現象に「なぜ」と問うことが第一歩
佐藤:なるほど。人間とマシンで競創すると考えると、AIが発達することで仕事が減るのでは、と怯えるのではなく、AIの発達は自らをブラッシュアップする意欲を喚起させる、素晴らしい機会だと捉えることができますね。競創に至る原点にはやはり独創があるかと思いますが、常に「なぜ」と問う視座は、どうすれば身につくものなのでしょうか?
石井先生:独創性あるアイデアを打ち立てるための、明確な方法論は存在しません。独創にあたっても重要なのは、本質的な問い、誰も問うたことのない問いを自分自身で問う力です。なので基礎教養としてのリベラルを身につけることは大切ですし、その意味で近いのは哲学やアートなどの人文系の分野といえるかもしれません。
ただ、常に新しい問いを新しい視座から発していく、その視座を確立するためにはリベラルアーツも、サイエンスも、テクノロジーも、AIも必要です。世界的な哲学者やアーティストが何らかの結論、作品にたどり着く過程から見えてくる道は、よく学んで自分なりに大きく目を開き、無限の興味を持って世界を観察する以外にない。誰も考えたことがない作品を生み出そうとしている時は、たとえ不完全な解答であってもその問いに対する世界で初めての答えを試みている状況に他なりません。そういう積み重ねが人間を前進させていきます。独自の視点、視座から物事を見ることで新しい発見があり、新しい問いが生まれるわけです。
佐藤:では先ほども仰っていたように、あらゆるものに興味・感心を持つことこそが第一歩であると。
石井先生:例えば、COVID-19(新型コロナウィルス、以下コロナ)に関連する事例だと皆さんにもわかりやすいと思います。皆さんは、ビニールシートのカーテン越しにハグをしている写真を見たことはあるでしょうか。人間はソーシャルな生き物なので、身体的な接触は極めて重要なコミュニケーションです。だからこそ、家族であれ恋人であれ、赤ちゃんとお母さんであれ、タッチは非常に本質的な行動なんです。それがコロナ禍によってアンタッチャブルになり、患者のベッドを訪問できない、最後の別れを言えない状況になるのがコロナでは最も苦しいことでした。これを何とかしたい、ソーシャルタッチができないコロナ禍の矛盾を背景に独創的な研究をやりたい、と思うことこそがモチベーションになるんです。
佐藤:確かに、コロナ患者が隔離されてしまう状況下では家族と面会ができず、強い不安に苛まれたという話も耳にしました。ビニールシート越しのハグと聞くと、石井先生の研究である「inFORM」が思い浮かびます。将来的には「inFORM」などの研究の活用によって、隔離患者との身体的接触が可能になるのでは、という期待が持てますね。
石井先生:応用的にはそういった用途も考えられますね。テレプレゼンスは、人類が抱いている夢といえます。我々は東京にいながらボストンに赴くことはできないわけで、唯一できるのがビデオカンファレンスです。しかし、画面の向こう側にいる人が落ち込んでいる時に手を伸ばして肩を叩いてあげたり、といったことはできない。特にこのコロナ禍のソーシャルでエモーショナルな関係においては、身体的な接触ができないことに関する限界を強く感じることになりました。それはピクセル、サウンド、そしてAVだけのやり取りだからです。
こうした状況を打ち壊すための手段がラディカル・アトムズ、つまりコンピューテーションによって形や性質をコントロールできるダイナミックなメディアであり、私の掲げるビジョンなんです。そして、ラディカル・アトムズというマテリアルを背景に、それをテレプレゼンスに使おうという応用のアイデアが複合して出来上がったのが「inFORM」であり、「ZOOMの次は何か」という問いに対して、多くの方が我々の「inFORM」を指し示してくださっています。メディアを使うことによって遠方にいる人の身体の一部を再現すると、「inFORM」でやっていたように画面の向こうにある赤いボールに触るといったことが可能になる。身体性が抜け落ちていることはそれだけ致命的な問題なのに、今まで誰もやったことがなかったこの問題に対するひとつの解答を「inFORM」として示すことができたのも、先ほどお話しした「独創・協創・競創」あってこそです。
佐藤:これまでに誰もやったことがないことを見出し、ビジョンとするのは並大抵のことではできないと思いますが、石井先生はどのようにしてビジョンを定められているのでしょうか?
石井先生:ビジョンというのは、ひとつの考え方としては妄想や夢想することといえます。
若干荒唐無稽であっても、「こんなことが起きたらいいな」「もしかしたらできるかもしれない」と夢を持つことがビジョンになるのです。私がタンジブル・ビッツを作り始めた時には、全ての情報はスクリーンの裏側にある光る点でしかなく、自分たちの身体を使って直接操作することはできませんでした。そこで、粘土や筆、そろばんなどを自由に扱えるように、情報をフィジカル世界に持ってこようと思い立ったのが30年前です。これはある種の妄想で、思いついた時にはほとんど意味がわからない状態でした。ですが、実際に30年間研究を続けて、具体的な「MusicBottles」「Illuminating Clay」、あるいは「SandScape」、「PingPongPlus」といった作品として発表することで、ようやく信じてもらえるようになりました。なので、そういう意味で夢を見るというのがビジョンの重要な要素のひとつです。
よく「日本人には◯◯の資質が欠けている」と言う方もいますが、私は全くそうは思いません。人種によってできること、できないことが明確にわかれているなんてことは有り得ないし、突出した個人は基本的に何でもできます。私もその一人になろうと思っていますし、日本人だから、日本企業だからビジョンなんて打ち出せるわけがない、とは考えて欲しくないですね。
企業のビジョンは「存在理由」を示すものでなければならない
佐藤:近年は明確なビジョンを打ち出す企業も増えてきましたが、企業としてビジョンを示す際に意識すべきことなどはあるでしょうか?
石井先生:企業としてビジョンを掲げたいなら、「企業がなぜ存在するのか」を問われた時に答えられるかが重要です。多くの方がBetter FutureやBetter Worldといった、いわゆる「もっと素敵な世界を作りたい」ということを仰います。ですが現実問題、世界は良くなるどころが悪い方へと進んでいってしまっている。「もっと素敵な世界」なんて、言ってしまえば内容のないスローガンをいくら叫んだところで、何も響きはしないんです。世界を平和にしたい、戦争をなくしたいと多くの人が思っているのに、なぜ戦争がなくならないかといえば、人類はそもそもそういう本質を持っているからです。
必要なのは美辞麗句的な言葉ではなく、企業が本当に真剣にやろうとしていることが、存在理由として言えるかどうか。グリーンウォッシングという言葉に象徴されますが、理念や社是に「地球環境に優しい企業を目指す」とうたっている企業は山ほどあっても、ほとんどが上辺だけに過ぎないんです。
佐藤:グリーンウォッシングは世界的に問題視されていますね。SDGsなどで環境意識が高まる半面、真に環境保護に向けて動けている企業は本当に数少ないのだと思わされます。
石井先生:そもそも、地球温暖化の原因そのものが、我々の生活の根本に資本主義があるからです。どんどん生産して消費する、そのメカニズム自体がすでに破綻しているんです。風力発電で得たエネルギーを使っているからクリーンだ、と言ったところで、市場には本来作る必然性がない製品が溢れています。地球に優しいリーズナブルな資源を使っていたとしても、ほぼほぼ誰もリユースしない。リユースにはお金と時間と手間がかかりますから、いらないものは捨てて新しいものを買った方が効率的なんです。
ファッションでたとえるなら、身体は1つで足も2本しかないのに、何千個もの靴があったって本当は意味がありません。ファッションのためにどんどん取り換えているだけで、実はその裏で多くの資源が消費されていることを考えれば非常に大きな問題です。都市の建設も同様で、役に立ちもしない、作る必要もない製品を世界中の企業が作り続けている。ですが、本当に必要なものを考えていけばその数は極めて少ないわけです。
佐藤:石井先生は先ほどビジョンについて一種の妄想や夢想であると仰っていましたが、例えばグリーンウォッシングにならないようなビジョンを打ち出すにはどうすれば良いのでしょうか?
石井先生:クリーンな企業を目指すのであれば、真剣にそれを示す証拠がなければいけません。代表的なのがパタゴニアという会社で、環境について語る時には必ず出てくるくらい有名です。パタゴニアくらい徹底的に、ストイックに取り組めばみんなが信じるし、企業の好感度も上がるでしょう。
先ほども言ったように、単に「地球と人に優しい未来を創る」と綺麗事を並べていても全く響かないので、これではビジョンとはいえません。研究においてビジョンを持つことはもちろん大切ですが、企業も存在理由を突き詰めて明確にした上で言語化し、従業員も顧客も説得できるだけのビジョンを打ち出さなければ、この先、生き抜いてはいけないと思います。逆に、明確なビジョンを示すことができれば100年後も生き延びることができる企業になるのではないでしょうか。
佐藤:仕事がしんどいばかりで何のためにやっているのかわからない、と社員に思われているような企業だと、これから仕事を探そうという若い人達に就職先として選んでもらいにくくなりますよね。
石井先生:そうですね。従業員・顧客が納得するビジョンは、優秀な人材確保のためにも重要なことなんです。そして強固なビジョンを作るためには、先ほどお話しした「独創・協創・競創」という3つのステップに加えて、「出杭力」「道程力」「造山力」が必要になります。
人と違うことをやろうとすれば、出る杭を打とうとしてくる人たちもいます。普通は打たれ続けたら脳挫傷を起こして、頭蓋骨陥没で終わってしまう。そこを生き抜くためには、尋常でない精神力、強い信念と意志が必要なんです。重要なのは突出しようとする意志ではなく、打たれた時にどう対抗するかを考えること。だから打たれても打たれても生き抜くための強い意志、「出杭力」(でるくいりょく)を持つことが大切なんです。
「道程力」とは、誰もいない原野に一人で踏み入って道を作ることを意味します。敬愛する高村孝太郎の詩「道程」からこの名前をいただきました。草や木を伐って、道を切り拓きながら自分一人だけでも全力疾走する力です。ただ、正直なところここまでのパイオニアであれば世界中にたくさんいます。
最も難しいのが「造山力」で、山のないところに山を作り上げる、そういう作業です。海抜ゼロメートルの何もないところから、世界中の人が登り始めるようなエベレストを作り上げていくんです。この「造山力」こそ私がMITで生き残るために学んだことであり、企業が100年後まで生き残そうとするならば、絶対に不可欠な考え方といえます。
どんな職業であってもオリジナリティは発揮できますし、磨くことは可能です。むしろ、どの業界でも創造性の尖った人が現れるのを求めている。だからどの業種にしろ、徹底的に自分の視点を磨き上げて、クリティカルな問いを発し続けてください。人と違った見方をして、それに対して一生懸命考える。その訓練を若い時からどれだけやるかが、分かれ目になるでしょう。
佐藤:「独創・協創・競創」という人間にしかできないことの本質から至るビジョンがあれば、AI社会においても自身のすべきことを見失うことは絶対になさそうです。最後に読者の方に向けてメッセージをお願いできますか?
石井先生:我々は今、解決しなければならない問題を世界中にごまんと抱えています。しかしどれひとつとっても非常に難しい問題ばかりで、実現しようとすればステークホルダーの利害が衝突してしまう。自分たちが実現しようとしたことで生じる新たな問題を、発展途上国を含む世界全体でどうやって負担・分担していくのかを考えなければならない。ですが、もうすでに地球上には負担・分担できる部分すら残っていません。また、戦争をはじめ、あまりにも根が深く、どうしようもできない問題もたくさんあります。なくなって欲しいと100回祈っても、1000回唱えても何も変わらない。そこで大切なのは、何から始めて自分がどう貢献していくのかを各自が考えることです。
だからこそ、ビジョンにはきちんと透徹した哲学があって、それが誰からも「確かに正しい」と賛同を得られるもので、自分自身も納得のいくものでなければ、存在理由がないんです。これからの世界では、我々一人ひとりがそういうビジョンを見つけなければいけません。これは個人としてだけでなく、企業の戦略的にも非常に重要だと思います。生きている間に何かを成し遂げたいと思ったなら、成し遂げたとみんながわかって自分も満足できる、そういう努力目標を持つべきです。まずは自分のできるところで何をするのか、何を残したいのかを明確にするところから始めてみてください。