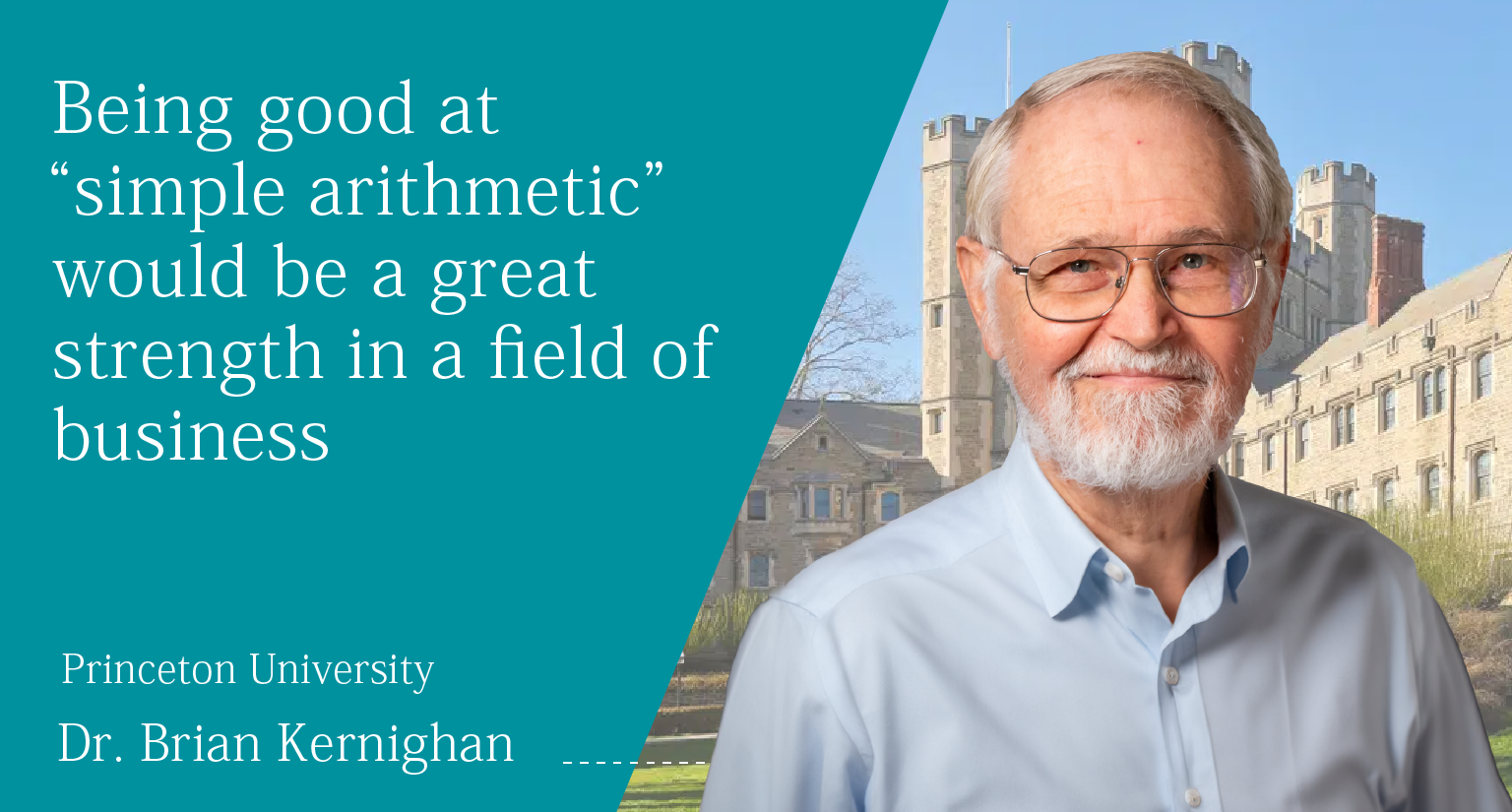2018年以降、政府によって「働き方改革」が進められていますが、未だ実感できないという方は多いのではないでしょうか?
経営側の立場としても、具体例や実践的なアイデアがなく二の足を踏んでしまっている、というケースは少なくないでしょう。
そこで今回は「働き方改革」の現状と今後、そして企業ごとに取り組めることについて、昭和女子大学の八代教授にインタビューしました!

取材にご協力頂いた方
昭和女子大学グローバルビジネス学部特命教授 八代尚宏
日本経済研究センター理事長、国際基督教大学教授等を経て現職。
専門は日本経済論、労働経済学、社会保障論。
主な著書は『少子高齢化の経済学』、『日本的雇用慣行の経済学(石橋湛山賞)』、『新自由主義の復権』、『シルバー民主主義』他。
エモーショナルリンク合同会社取材担当(以下EL):最初に、「働き方改革」の概要について教えていただけますか?
八代教授:政府の考えとしては「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」や「育児や介護との両立など働くニーズの多様化」への対応など、現行制度を前提とした、経済社会の変化への対処を目的としているようです。
とはいえ、現行制度前提では限界があるのも事実です。長期雇用・年功賃金といった従来の日本的雇用慣行そのものを見直すことが、本来の「働き方改革」には不可欠になります。日本の雇用慣行は、過去の高い経済成長と豊富な若年労働等の社会環境の下で効率的であった集団単位の働き方の仕組みでしたが、そうした状況は大きく変化しているためですね。
EL:ありがとうございます。それでは、政府の掲げる「働き方改革」は現状どこまで進んでいるのでしょうか?
八代教授:「働き方改革」によって最も成果が見られたのは、残業時間の抑制でしょう。
そもそも、政府が「働き方改革」について言い出したきっかけは過労死問題なのです。長時間労働を是正しなければいけない、ということで労働基準法を改正して、残業時間の上限を決めた。このことについては高く評価できます。
それでは政府は、それまで何もしなかったのかというと、そういうことではなく、残業時間の上限規制はすでにあったのです。ただ、この制限というのが組合と合意すれば取っ払ってしまえる、という甘い内容でした。個々の労働組合は残業を歓迎する場合が多いので、はっきり言って、既存の上限規制にはほとんど意味がなかったわけです。
EL:確かに、それでは残業時間を無限に増やせることになってしまいます。
八代教授:だからこそ、「働き方改革」に伴って組合が合意しても動かせない、残業時間の絶対的な上限を課したことには大きな意味があります。実際、2021年の労働力調査では長時間残業をしている人が8年前に比べて4割ほど減っています。残業をほとんどしない人もいるので、平均的な残業時間ではなく、週40時間を基準として、週60時間以上働いている人、つまり1日4時間以上残業している人の比率です。こうして見ると、サービス残業は別として、長時間労働は減っているとみられますので、そういう意味での「働き方改革」は進んでいるといえます。
EL:2022年の今でも長時間労働が取り沙汰されることはありますが、データとして見れば確実に減少しているのですね。
八代教授:そういうことです。もうひとつ変化が起きているのは、女性が働く時の大きな制約になる配偶者手当の存在です。
平均で1万円、大企業だと月5万円ほどの手当がつくこともあって結構な金額なので、なくなると困るわけですね。しかも配偶者手当の基準は税制上の配偶者控除にリンクしますから、控除がないと手当ももらえない。つまり、奥さんが控除を受けられないほど稼いでしまうと手当がもらえなくて、夫としては給料が減ってしまうことになる。だから奥さんに対して働くなら手当がもらえる範囲に抑えて、それ以上は働くなという圧力があるわけです。
EL:収入を減らさないために働くな、となると、働く意欲自体を削ぐことになってしまいそうですね。
八代教授:このことに関しては、本当は政府が配偶者控除をやめるべきなんですが、今のところなかなか進んでいません。
ただ、配偶者控除については企業の努力で変わってきている部分があります。例えば、トヨタ自動車は配偶者手当を廃止することを決定したんです。しかも、ただ廃止するだけだと社員の収入が減ってしまうので、月1万9,500円の配偶者手当をなくして、その分子ども1人あたり5,000円だった手当を2万円に増やすという形を取ったんですね。結果的に養う子どもが1人以上いる家庭ならこれまでと同じか、より多く手当がもらえることになりました。
このように、政府が配偶者控除をやめなくても企業努力で対応できる範囲というものはあるわけです。
EL:企業が自ら「働き方改革」を先導する動きを見せているというのは、他の企業にとってもお手本になりますね。
八代教授:ただ、トヨタ自動車の例でも問題はあって、子どもを持っている家族にとっては望ましくても、子どもが大きくなって独立している高年齢世帯ではかえって収入が減ってしまうんですよ。
配偶者手当の問題は、よく男女間の対立のように言う人もいますが、正しくは世代間の対立です。子どもはアルバイト以外は働かないので、いくら手当をつけても就業抑制効果はない。ですが奥さんは働くと損する仕組みになってしまっている。この世代間対立をどう克服するか、が大きな問題になるわけです。
人口が減ってきて女性にも働いてもらわなければいけないという時代に、こういう「働くと損をする」仕組みになっていることは問題ですです。今のところはトヨタ自動車などの先進的な企業では望ましい改革が進んでいる、ということですね。
EL:ありがとうございます。先ほど残業時間についてのお話がありましたが、日本で残業がなくならないのはなぜなのでしょうか?
八代教授:まず、余暇よりも残業代が欲しい中高年が多いという面もありますが、一番大きいのは雇用保障です。
そもそも残業割増率の下限をなぜ法律で決めているかというと、できるだけ企業が労働者を残業させないために、残業でコストが増えるようにしているのです。
これはアメリカの企業には有効な方法で、アメリカの企業はとにかく残業はさせずに、仕事が増えたら追加で労働者を雇います。アメリカでは労働者の調整が自由なので、不況になればレイオフ(一時解雇)して人件費をカットできる。ですが日本の場合は一度雇ったら簡単には解雇できませんから、不況でも対応できるように、普段から少なめの労働者で回しておいて、常に残業させているんです。
アメリカのように労働者の数をカットする代わりに、日本では不況に労働時間をカットして対応する、というやり方の違いがあります。言ってしまえば、日本では企業にとっても労働者にとっても残業は不可欠なのです。
EL:残業をすることが良い、悪いではなく、日本の制度的な問題なのですね。
八代教授:本当に残業をやめさせようと思ったら、不況期のレイオフを認める必要がありますね。
ひとつ例を挙げると、日本でも、あるタクシー会社がコロナショックでお客さんが当分増える見込みがないから、運転手の何割かを組合の同意を得て米国のような一時解雇をしようとしました。ただ、解雇はするけれども、コロナが収束したら必ず雇うと約束しますと。しかし厚労省がそれを認めず、いずれ呼び戻すなら失業者ではないとして失業手当を支払わないとしました。この硬直的な対応の結果、よりコストのかかる休業補償で対応しなければなりませんでした。
また、海外との違いという面で見れば、有給休暇の取得率の低さも日本の労働時間が長い一因です。
最近ようやく5割ほどになりましたが、20日間の有給休暇があったとしても、それを全部使いきるのは無理なんです。これに対して、私が以前に勤務していたパリの国際機関では、バカンスで、8月いっぱいは皆ほとんどいないんです。9月に帰ってくるとどこが良かった、と情報交換をして、来年の8月分の予約までしてしまう。日本なら1年先の休暇の予約なんてできないわけですが、なぜフランスではそれができるかというと、自分の仕事に合わせて休みを取れるからなんです。日本でも自分の仕事範囲が明確な、個人単位の働き方に変えなければ、とても有給休暇の消化は進みません。
日本人が働きすぎとみられるのは、文化の違いではなく、長期雇用保障と集団的な働き方の下での企業内訓練重視という仕組みから、必然的に出てくる問題と言えましょう。
EL:こうしてお話を聞いていると、日本は海外に比べてずいぶん遅れている印象を受けます。
八代教授:そうですね。コロナ禍以降導入が進んだテレワークも、外国では当たり前に行われています。
テレワークはホワイトカラーの働き方の効率化には欠かせません。ですが、日本ではずっと満員電車に乗ってオフィスに行って、オフィスでパソコンを使って仕事をしてきました。それなら自宅でパソコンを使って働くのと何が違うんだ、となりますね。コロナショックによって日本でもある程度までテレワークが普及したことは、怪我の功名のようなものです。
テレワークが進めば時間の効率化につながりますし、通勤の疲労も減ります。子育てや介護と仕事との両立にも大きなメリットがあります。なのに今までテレワークの導入が進んでいなかったのが、コロナの感染防止という外部からの圧力でようやく実現したわけですね。
揺り戻しはありますが、数字を見るとコロナショック以降テレワークの比率は確実に上がっています。コロナの後は一時50〜60%ほどまでいっていたんですが、今の平均だと27%ほどです。
EL:今データでも示していただいた通り、コロナショックでテレワークを導入した企業が再びオフィスワーク主体に戻る動きも見られますね。日本でテレワークの定着は難しいのでしょうか?
八代教授:この先、テレワークを定着させるには、やはり政府が労働基準法を変えていかなければいけません。それは、本格的な裁量労働制や個人の仕事範囲の明確化など、働き方の大きな変化なしには困難なためです。
まず裁量労働制の拡大です。今の日本の労働法というのは、昔の工場労働者の働き方を前提にしています。簡単にいうと、ベルが鳴ったら一斉に働き始めて、ベルが鳴ったら一斉にやめる集団的な働き方です。こういう働き方だと、労働者が1時間プラスして働けば確実に1時間分の製品はできるわけで、だからこそ働いた時間に比例した残業手当を出すことに意味があります。
ですがホワイトカラーの仕事というのは、1時間余分に机の前に座っていたからといって追加のアウトプットがあるとは限らない。労働時間と報酬を厳格に結びつけるのは工場労働者にとってはいいことですが、裁量的な働き方のホワイトカラーの場合は本来結びつけてはいけないのです。ホワイトカラーで労働時間に対して報酬を出すと、効率的に働いて8時間で仕事を終える人よりも、だらだら働いて残業する人の方が賃金が増えるという、不公平で非効率的な働き方になってしまいます。
EL:もともと工場労働者向けに作った労働基準法が、ホワイトカラーにも機械的に適用されてしまっているのですね。
八代教授:これは全く望ましくないので、1日に実際に働いた時間に関わらず給料が変わらない、裁量労働制を本格的に取り入れる必要があります。
私たちのような大学教員や、テレビのディレクター、新聞記者の人なんかも外国では裁量労働制なんですが、日本では部分的にしか適用されていません。1日何時間働いても給料は同じはずなのに、休日と深夜勤務については残業代を受け取らなければいけない。今の日本では、裁量労働制であっても残業や休日出勤は適用除外になるんです。
なぜこれが問題かというと、例えば、テレビのディレクターが、昼頃に出勤してきて深夜まで働くと残業代が出るわけですよ。銀行の仕事で、外国と取引する時は時差があって働くのは深夜になるので、朝いても仕方がない。なのに定時に出勤して深夜勤務分の割増賃金は発生しますが、その分、疲労も溜まります。
裁量労働制であれば、本当はこういう仕組みはおかしいんです。今挙げたような人たちは、必要な時間である夕方から自由に出勤して働くことが本来は望ましいわけですね。
だからこそ、本格的な裁量労働制を政府も取り入れるべきなんですが、労働組合の猛反対に遭っているという状況です。もっとも、日本の労働者、特にホワイトカラーは仕事の範囲が明確ではないので、効率的に働ける人にはどんどん別の仕事が回ってくるから残業代がないとキリがない、という面に関しては労働組合の言うこともある程度正しいかもしれません。
そこで重要になるのが、裁量労働制と同時に個人の仕事の範囲を明確化しておくことです。
EL:仕事の範囲を明確化するというと、具体的にはどういった内容なのでしょうか?
八代教授:私はOECD(経済協力開発機構)という国際機関で3年間働いていたことがありましたが、本当にすごいなと思ったのが、今お話ししたように仕事が明確に決まっていたことなんですね。他の人の仕事に手を出してはいけないし、自分の仕事さえやればいいので何時間働くかというのは全くの自由なんですよ。だから、今日は用事があるから早く帰って、明日は余分に働く、というのを個人の裁量でできるんです。
だから残業という概念自体もないんですが、日本でそれができないのはやはり個人の仕事の範囲が明確ではなくて、勝手に昼間いなくなってしまったりすると同僚に迷惑をかけてしまうからなんですね。サボっているわけでなくても、仕事が一番遅い人に合わせていると残業時間は延びてしまいがちです。
EL:確かに、日本だと仕事は個人で完結させるというより、誰かが遅れたら全体でサポートするといった意識が強いように感じます。
八代教授:集団的に働くとどうしてもそうなってしまうので、本格的な裁量労働制の実現には仕事の範囲を明確にすることを先にやらないといけません。仕事の範囲の明確化は選択的週休3日制にも深く関係するのですが、聞いたことはありますか?
EL:耳にすることはありますが、具体的には理解できていないと思います。
八代教授:週休3日制についてよく言われるのは「週休2日で十分なのに何で3日も必要なのか」という批判なんですが、はっきり言って週休2日とは全然違うものです。
「選択」というのがキーワードで、例えば個人が自分で土日以外にこの日に休む、と決めます。月曜日でも木曜日でも金曜日でも、あるいは休まなくてもいいんですが、週休2日のように一斉に休むということではなく、バラバラに休むわけです。もちろん労働時間は同じなので、週3日休む人は他の4日間にそれだけ長く働くことになります。
それでも、共働き世帯なんかで夫と妻がそれぞれ別の日に休みを取れば、子育ては非常に楽になりますよね。介護もそうですし、4日間集中的に働くことによって生産性の向上も期待できるので、導入によるメリットは多いわけです。
EL:積極的に取り入れることで働き方の自由度も大きく向上しそうです。あまり導入企業の話は聞かないのですが、選択的週休3日制をなかなか採用できない理由は何なのでしょうか?
八代教授:選択的週休3日制で何より大事なのは、全員が揃っていなくても仕事ができる体制を整えることです。
土日を除いて特定の日に常に休んでいる人がいるというのは、今までの日本企業にはない状況でした。なので、実現するには徹底した情報共有が必要で、上司が休んでいるからハンコが取れないといったことは許されません。上司が休んでいても仕事は進む、という体制を作らなければいけない。導入できれば生産性を非常に向上させますが、実現するにはやはり個人の仕事の範囲を明確にしておかなければ難しいわけです。
EL:一口に「働き方改革」を進めるといっても、様々な要素が複合的に絡み合っているために、根本的な部分から見直していかなければいけないのですね。
八代教授:その通りです。日本の企業というのは、大学や高校を出たばかりの全くの未熟練者を喜んで採用してくれる、世界にもまれな企業なんです。
外国では何らかのスキルがなければ基本的に雇ってもらえないので、若年失業者が溢れています。OECDなんかは新人訓練は一切せずに、最初から仕事ができる人を雇います。ですが、日本は新卒一括採用の関係で未熟練者でも雇ってもらえる。その人が仕事でいろいろな経験をして熟練労働者になっていくわけですが、それは先輩や上司が仕事を教えてくれるからなんですね。
だから、OJT(職場での実践を通じて業務知識を身につける育成手法)は逆に日本の集団的な働き方の良い面といえます。
ただ、仕事を教えるためには同じ場所に、同じ時間一緒にいなければいけない。つまり、集団的な働き方には集団で働くことを通じて訓練をしていく、という非常に重要な役割があるわけです。働き方にはそれぞれにメリット・デメリットがあって、OJTにもいい部分はありますが、全員が同じ時間に同じ場所にいなければいけないから非常に効率が悪い。だからテレワークもなかなか進まない、という面もあります。
一言でいえば、日本の働き方というのは過去の高い経済成長期には合っていたんです。成長率が高ければ企業の仕事もどんどん増えますから、何でもできる労働者が必要とされました。欧米のように、これしかやりません、では困ってしまう。ですが日本ももう時代が変わって低成長ですから、従来の働き方をやめていかなければいけない時期にきていますね。
EL:本当に、先生の仰る通りだと思います。今後は最初にお話しいただいたトヨタ自動車のように、企業が自ら動いていくことも重要になるかと思いますが、経営側の立場から取り組める施策を教えていただけないでしょうか?
八代教授:日本の企業で導入できることとしては、まず人事評価の仕組み作りをおすすめします。
日本の企業だと、技術者を無理やり課長にして辞められてしまうケースがありますよね。技術者の中には、自分の研究はしたいけれども部下の管理まではしたくない、という人も結構いるんです。
これは仕事の範囲の明確化にもつながってくるんですが、日本は特に40歳くらいになったら誰でも管理職になります。逆に言えば管理職なんて誰でもできる仕事だ、という意識も強いわけですが、それは冗談じゃない話で、管理職ほど重要な仕事はないんです。私も20年間官庁で働いていましたが、仕事ができない管理職の下につくと部下はひどい目に遭うんですね。少なくとも課長以上の人というのは、本当に能力の高い人にしないと周りも困りますし、会社全体としても効率性が落ちることは明らかです。
EL:私の友人でも、技術者系の人で年齢から無理やり管理職にさせられて、結局会社を辞めてしまったということがありました。年齢よりも適正で役職を決めて欲しい、と思うことは多いですね。
八代教授:だから、OECDでは管理職を決める時に手を挙げさせるんですよ。それからその人でいいかをパネルディスカッションなんかで議論するんですが、日本でやったら全員が手を挙げるから意味がないんです。OECDではなぜ全員が手を挙げないかといえば、管理職が大変な仕事だと皆がわかっているからなんですね。
OECDは人事評価にものすごく時間をかけます。日本でも人事評価は行いますが、ほとんどは上司が部下を一方的に評価して人事部に送るようなことしかやっていない。そうなると上司の主観が強く入って最悪好き嫌いで決まってしまうし、部下も反論ができません。
ですが、OECDの人事評価の仕組みでは、まず上司が私のパフォーマンスについてA・B・C・Dといった段階評価と文章での評価をして、それを部下である私自身が見て確認したというサインをします。もし異議があれば記入欄まできちんと用意されていて、上司の上司がそれを見てサポートしてくれるんです。
EL:素晴らしいですね。そういった人事評価の仕組みが導入されていれば、働く時のモチベーションにもつながりそうです。
八代教授:ただ、こういう仕組みだと、課長以上の管理職というのは非常に大変な仕事なんです。
これをどこかの会社で説明したら「課長がノイローゼになってしまう」と人事部に言われましたが、そんなことでノイローゼになる人は課長にしてはいけないんですよ。管理職の最大の仕事は、部下がきちんと働けるための人事評価です。
能力にしても、日本なら部下が病気になって休んだり、辞めてしまったりしたら別の部下に仕事を頼めます。ですが個人の仕事範囲が明確化されていたら、課長がそれをカバーするしかありません。なので管理職は自分のどの部下よりも仕事がよくできる人でなければいけないんです。OECDのような場所だと部下は定時に帰って課長だけ残って残業する、なんてことは当たり前なので、そこまでして管理職になりたくないという人もいるんですね。それでもなりたい、というワークホリックな人だけが管理職になればいいわけです。
こうやって、課長なんかの管理職になるかならないかを自分で決める権利を与えると、専門職としてきちんとした処遇ができるようになります。今お話ししたような働き方というのは欧米から学べる部分が多いので、仕事の効率化の面から見ても非常に重要だと思います。
EL:大変参考になるお話、ありがとうございます。最後に、起業を考えている方や経営者の方に向けて、メッセージをいただけますか?
八代教授:人事評価制度の整備や管理職を専門職として扱うこと、各自の仕事の明確化などは、企業ごとに実践できる部分です。
加えて昨今では、企業のパフォーマンスとしても女性管理職比率や男女間の賃金格差などが取り上げられるようになっています。投資家や株主が企業を見る時には、これに加えて、配偶者手当の有無や選択的週休3日制などの「働き方改革」に積極的に取り組んでいるかどうかも、今後は企業の生産性や成長性を測る重要な指標の1つになるでしょう。
先進的な働き方を行う企業が増えるほど、政府が制度改革に動く可能性も高まるので、ぜひ積極的に取り組んでいって欲しいですね。
まとめ
政府主導では進めにくい改革も、企業が単独で実現している事例があると知れたことは非常に参考になりました。
また、八代教授も仰っていたように、先進的な取り組みを行う企業は自然と社会的評価も高まっていくと考えられます。会社を成長させていく上で、「働き方改革」への意識は今後欠かせないものとなっていきそうです。
これから起業を考えている方も、海外の働き方を参考に、取り入れられる部分を主体的に導入していくことが望まれますね。
関連資料
- 『経済学で考える人事労務・社会保険』『(月刊)ビジネスガイド(連載)』日本法令
- 『日本経済論・入門―戦後復興からアベノミクスまで』有斐閣
(取材・執筆・編集/エモーショナルリンク合同会社)