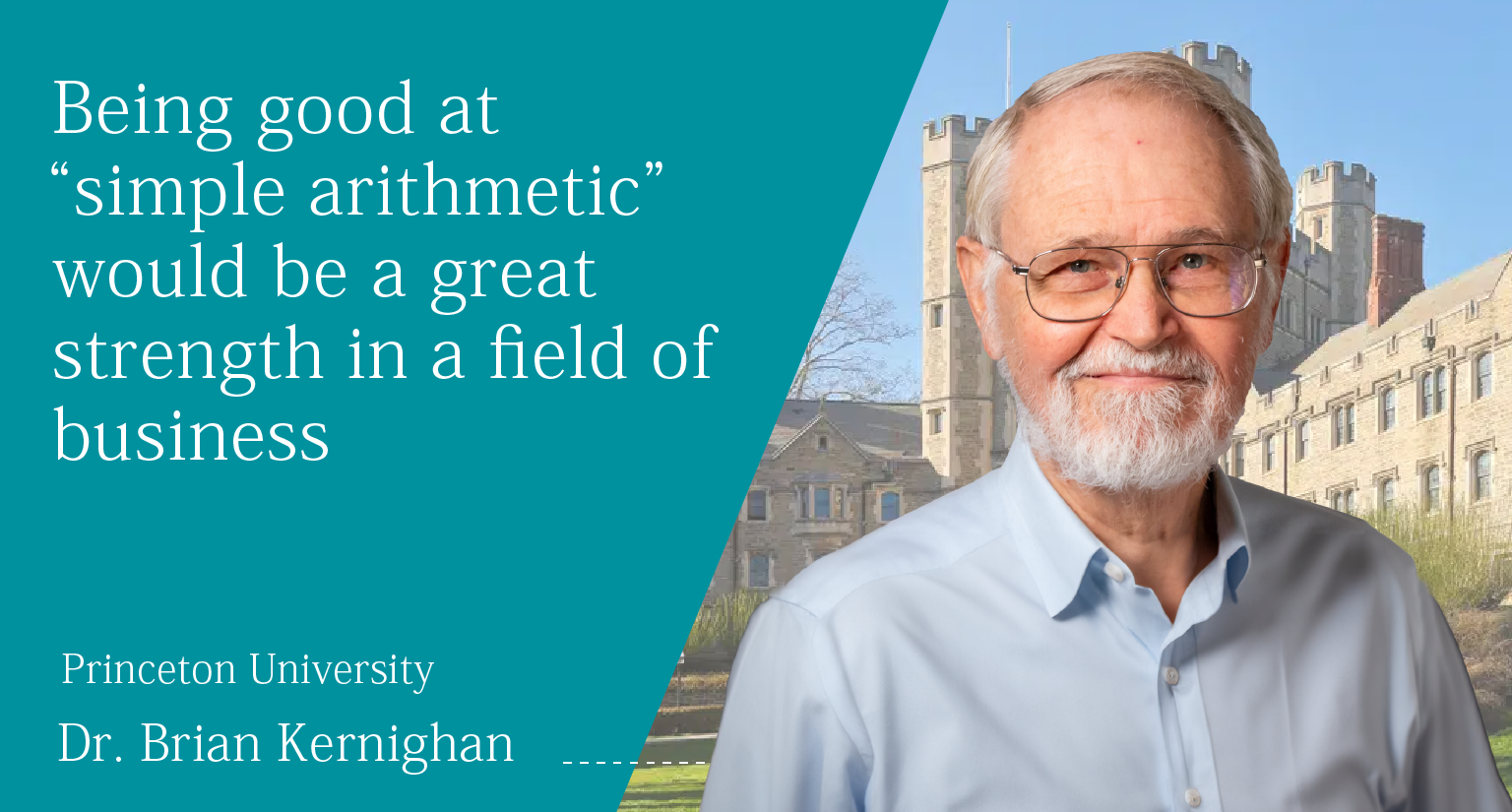今日の次には明日があり、今年の次には来年があり、この10年の次には次の10年がある。そして現在の日本経済は過去からの文脈の中にあります。今どうなっているのか?ということを相対化して捉えるには歴史的な視点が欠かせませんし、それはこの先にある未来を考えるためにも大切な要素になるでしょう。
そこで今回は、日本経済史がご専門のフェリス女学院大学齊藤直教授にお話を伺いました。過去から何を学び、それをどのように生かせば良いかという視点から、戦前から現代に至るまでの日本経済史について、以下のテーマから教えていただいています。
- 戦前〜現代にかけての日本経済史の特徴
- 戦後〜平成期の日本経済の変化と、バブル崩壊の10年間から学べること
- 現代の日本経済が持つ課題
- 歴史から何を学び、どう生かせば良いか
現在、そしてこれからの日本を考える上で大切なことを、歴史から学ぶことができるでしょう。
それでは早速見ていきましょう。

取材にご協力頂いた方
フェリス女学院大学 国際交流学部 教授
齊藤直(さいとうなお)
現職:フェリス女学院大学 国際交流学部 教授、早稲田大学 商学部 非常勤講師、駒澤大学 経済学部 非常勤講師 ほか
早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程を修了し、博士(商学)を取得。2010年にフェリス女学院大学国際交流学部准教授に就任、2017年より現職。
著書:『国策会社の経営史』岩波書店、2021、『産業経営史シリーズ11:金融業』日本経営史研究所、2019、『現代日本経済 第4版』有斐閣、2019、ほか
戦前〜現代にかけての日本経済史の特徴
エモーショナルリンク合同会社取材担当(以下EL):齊藤先生、本日はよろしくお願いいたします。
齊藤先生:よろしくお願いします。
EL:本格的な経済史の話題に入る前に、第1章では基礎的な内容を伺っていきたいと思います。先生が専門にされている「経済史」とは、そもそもどういう学問なのでしょうか?
齊藤先生:経済史=経済+史、ですので、経済学と歴史学の間にある学際的な分野ということになります。どちらに力点を置くのかという点については多様で、この分野の研究者のなかでもだいぶ異なりますね。
経済学に近い研究者は、経済理論を応用して、歴史上の重要な事象に普遍性を見出そうという姿勢で説明しようとする傾向が強いですし、歴史学に近い研究者は史実を前提として、それが1回限りの出来事であることを尊重する姿勢で、特定の理論を前提とせず説明しようとする傾向が強いといえます。
重要なのは、双方の立場がお互いに反目せず、それぞれに重要な役割があることを認識したうえで、相手の立場を尊重して、議論を深めていくことだと思います。
EL:ありがとうございます。続いて、日本経済史の特徴について伺いたいと思います。特に戦前〜現代にかけて経済活動のあり方は大きく変化していると思いますが、この期間の日本経済にはどんな特徴があるのでしょうか?
齊藤先生:日本経済の特徴についてですが、特定の特徴が常にあるいは長期間にわたって見られるというよりも、時間の経過とともに、特徴を大きく変えてきたことが特徴であるといえるかもしれません。
別の捉え方をすれば、人々が当たり前のように日本経済の特徴だと考えていることが、わずかな期間のみ成立していた特徴であるということもあります。
例えば、最近は変わりつつありますが、1990年代に変化が起こるまで、日本の大企業では「終身雇用」とまで表現される長期雇用が当然のことと考えられていました。それが日本の社会に根付いた、当然のことであると考える人もいるかもしれません。
しかし、歴史を遡って戦前まで視野に入れれば、長期雇用は全く当然のことではありません。むしろ、経営環境が悪化し、それに何らかの対応をしなければならない場合には、速やかに雇用の削減が行われるというのが戦前の日本企業の特徴でした。既存の研究からは、雇用調整の速度は、戦前の日本において、非常に速かったことが知られています。
長期雇用が後退しつつある近年の状況のなかで、雇用の重視は日本社会に根差す伝統であり維持すべきだ、失われるべきではないと言わんが如き意見もありますが、「終身雇用」は戦後のある時期(せいぜい20-30年間)に存在したに過ぎないという史実を踏まえれば、それが日本的なものだという見解がそもそも慎重に捉えられるべきであることがわかります。
EL:一度就職すれば同じ会社で定年を迎える、という雇用のあり方が日本的な特徴だと思っていましたが、経済史の中では一つの場面に過ぎないというのは驚きです。
齊藤先生:同様に、1980年代頃までの日本の大企業では、株主が経営に対して口出ししないのが当然であるかのような状況でした。最近でも、株主が経営に対して積極的に発言したことを報じるニュースがあると、日本企業らしくないと捉える向きがあるようです。
しかし、これも戦後のある一時期だけに当てはまる特徴です。戦前の大企業では、株主の発言力は非常に大きく、戦後とは全く異なる状況でした。
EL:いわゆる「物言う株主」という言葉が、ニュースなどで聞かれることがありますよね。株主に発言力があった時代が、現代だけではなく戦前にもあったというのは興味深いですし、現代の日本人の多くが当たり前と思いそうな習慣が、必ずしも古くからある伝統ではないということも目から鱗です。
齊藤先生:そうですね。この二つの例からも見えてくるように、現状を絶対視せず、相対化するために、歴史研究が果たす役割は大きいと思います。
戦後〜平成期の日本経済の変化と、バブル崩壊の10年間から学べること
EL:ここからは、特に戦後〜平成期の日本経済史に注目していきたいと思います。この期間の日本経済の出来事、そしてそこからどのようなことを学べるかを教えていただきたいです。
齊藤先生:1990年代って、興味深いことが多く起こってますよね。80年代までと2000年代以降、その間にバブル崩壊後の10年間の混乱がありました。バブル前後はマクロ経済が落ち着いていますが、構造としては全く違うマクロ経済になっています。
例えば80年代までは、高度経済成長期よりは経済成長率が下がりましたが、成長するときには消費者に成果が還元されています。
また、2000年代と2010年代はいずれも長期的に景気の良い時期がありましたが、「実感なき景気」、「実感なき経済成長」といわれることもありますね。株価も上がっている、企業も設備投資をしているといった経済の好調さを示すさまざまな要素はあるのですが、しかし実感がともなわず、一般の人までは富が回らない。
こうした時代の間にあるのが、バブル崩壊からの90年代です。この10年間に何が起こったかは、丹念に考えないといけません。
EL:戦後の日本経済を考える上で外せないのは、90年代に起きた様々な動きとその歴史的背景になりそうですね。そして、現代の私たちにとっても、その一連の流れから学べることは多そうです。
齊藤先生:そうですね。ここからしばらく、バブル崩壊から不良債権問題に至るまでの流れを見ていきたいと思います。
EL:ここからは歴史のお勉強ですね!
齊藤先生:1980年代末の日本でバブルが発生し、90年代に入ってそれが崩壊し、100兆円に及ぶ不良債権を銀行が抱えて、金融システムが機能不全に陥るという問題がありました。いわゆる「不良債権問題」ですね。
不良債権問題、という用語はもう忘れられているかもしれませんが、日本経済が長期的に低迷したことで「失われた10年」と呼ばれたことは、その後、「10年」を「20年」、「30年」を延長して表現することもあることから、記憶している人も多いかもしれません。
EL:100兆円の不良債権とは、気が遠くなるような金額です。そもそもバブルはなぜ発生したのでしょうか?
齊藤先生:バブル崩壊を契機として起こったこの問題は日本経済に極めて深刻な影響を与えましたので、「なぜバブルが起こったのか」、「あそこまでバブルが過熱化するのを防げなかったののはなぜか」というような意識が出てくるのは当然です。
バブル発生の理由はいくつもありますが、ここでは二つだけ挙げます。
一つは、日本銀行が低金利政策を続けたことで、資産市場に資金が流入し続けたこと。
もう一つは、金融自由化によって従来は貸出先であった企業の「銀行離れ」が生じていた銀行が、不動産関連融資を拡大したことが、不動産市場への資金流入を促進したことです。
EL:原因がわかっているなら、当時の判断は正しかったのか、文句の一つも言いたくなりますが…。
齊藤先生:「日本銀行は政策を誤って、けしからん」とか、「やみくもに不動産関連融資を増やした銀行はバブルの主犯だ」というような見解が出てきても不思議ではないでしょう。
もちろん、結果責任としての日銀や民間銀行の責任を否定するつもりはありません。しかし、当時の状況をふまえれば、必ずしもそうした断罪のみで適切な解釈に到達できないように思います。それは戦犯探しに過ぎません。
EL:バブルの発生と崩壊は結果であって、その過程をよく調べれば、一つ一つの判断は必ずしも誤りではなかった、ということでしょうか。
齊藤先生:例えば、1980年代後半の日本銀行は、多額の貿易黒字という貿易不均衡が生じていた同時期の日米関係を考慮して、対米投資を積極化し資本収支を赤字にさせるために低金利政策を継続しました。単にバブルを過熱させるか抑制するかという点のみを考えていたわけではなく、対米関係という重要な問題をも視野に入れたうえで、国内の経済状況への対応との間で難しい綱渡りをしていたと考えれば、金利引き上げが遅れたことを、単に日銀が判断を誤ったとするのは単純に過ぎる評価であるといえます。
一方、民間銀行についてです。後に多額の不良債権が発生したことを踏まえれば、不動産関連融資をあそこまで拡大する必要はなかったであろう、という程度問題はあります。銀行の責任がゼロであると言いたいわけではありません。しかし、金融自由化の進展に伴う「銀行離れ」により、新たな貸出先が模索される状況で、実際に有力な貸出先はそうそうあるわけではありません。
また、他の業務の拡大を模索しようとしても、金融自由化のうち業務分野規制の緩和は遅れていましたので、それは非現実的です。もちろん、論理的な可能性としては、預金の受け入れを減らして銀行業務を縮小するという選択肢もありますが、既存の正規従業員の雇用を守ることが重要な課題とされる日本的経営の下において、そうした選択肢を実際に選択することはあまりに非現実的です。そうした状況下に、不動産関連融資の拡大以外の選択をすることができたはずだと考え、全てを銀行の責任に帰すのは、一方的な議論であるように思われます。
EL:当時の国際情勢や社会の状況を考慮すれば、のちにバブルの発生と崩壊を招く原因となった対応も、間違いとは言えなかったんですね。
齊藤先生:次に不良債権問題について見ていきましょう。
不良債権問題の深刻化に影響を与えた要因の1つとして、1990年代に銀行経営に対して導入されたBIS規制の影響を挙げることができます。
現在では、バージョンアップして「バーゼル3」と呼ばれている規制ですが、国際的な業務を営もうとする銀行に、一定の健全性を維持させるために、自己資本比率を一定の比率以上にすることを義務付けるものです。
このBIS規制が、1992年度決算(93年3月期)から日本の銀行に導入されたのですが、その際に何が起こったかといえば、規制が期待している効果ではなく、当時の日本で深刻であった不良債権問題をさらに深刻化、長期化させるという、非常に大きな副作用をもたらすわけです。
EL:経済史って面白いですね。良かれと思ってやったことが、見事に裏目に出てしまう。どことなく共感を覚えますが、そんなに悪さをするBIS規制なら、当時の人々は事前に副作用に気づかなかったのでしょうか?
齊藤先生:普通に考えれば、BIS規制について以下の点は、おそらく多くの人が理解している、あるいは、多少は意見の相違が出てくる点も含まれますが、概ね同意できる、といった点ばかりのはずです。
- 1990年代を迎える頃には経済のグローバル化も進み、大企業であれば、国境をまたいで事業を展開するのは当然の状況であった。
- そうした大企業と取引しようとすれば、自動的に、銀行も国際的な業務を営むことになる。
- 国ごとに金融規制・金融行政のあり方は異なっており、銀行は自国の規制・行政に従っているため、求められる経営の健全性にも差がある。
- そもそも、銀行は預金として受け入れた資金を貸出などの形で運用するが、預かった資金を常に引出しに対応できる形で保有しているわけではないため、急に多額の預金引出しが発生した場合には対応できないという状況にある。
- 金融業では、資金決済の取引はネットワーク状に広がっており、仮に1行でも銀行の経営状況に不安が持たれる状況になると、それが連鎖的に広がり、決済システムが機能不全に陥るとともに、各国の金融システム、さらにはマクロ経済に対しても多大な打撃を与えることになる。
- したがって、経済のグローバル化が進展した状況では、国際業務に進出しようとする銀行に、一定の健全性を求めることは自然な発想となる。
- 何をもって銀行の健全性を表現するかについては唯一の正解があるわけではないが、自己資本比率であれば、(自己資本は預金のようにいつ引き出されるかわからない資金ではないため、)数値が高ければ高いほど健全性が高いといえる。
- 以上を踏まえて、自己資本比率に着目した国際的な健全性規制を銀行経営に対して導入する。
EL:確かに、どこにも悪いところは見えませんし、これならむしろBIS規制導入賛成!といえそうです。それではなぜこのBIS規制が、当時の日本にあった不良債権問題をさらに深刻化させることにつながったのでしょうか?
齊藤先生:1990年代前半の状況を踏まえれば、バブル崩壊後で株価が低迷し、銀行の経営も悪化していっている状況下で、増資により自己資本を増強することは困難です。
とすれば、BIS規制の分母にあたるリスクアセット(株式や外国為替など、リスクのある資産のこと)を減らすしかないことになります。これが貸出を圧縮する誘因を銀行に与えることになります。あるいは、当時のBIS規制ではリスクウェイトがゼロであった国債を保有しようとする誘因も生じさせます。実際、1990年代後半には銀行による国債の保有が増加します。
さらに不良債権処理についても、一気に多額の損失を計上すれば自己資本を毀損することになりますので、自己資本を毀損しない範囲内で根気強く損失処理していくことになります。むしろ、多額の不良債権を発生させている問題の大きな取引先に対しては、追加融資(「追い貸し」)により不良債権ではないかのように見せかける誘因すら生じさせます。以上の結果として、問題がない取引先ほど貸出が減少し、問題が大きな取引先ほど多額の貸出が残る(場合によっては増加する)という状況が生じます。金融システムの機能不全というべき状況です。
銀行が貸出への姿勢を消極化させていますので、金融緩和の効果も得づらい状況です。そうしたなかで、1990年代末には、その後長く続くことになる非伝統的金融政策と呼ばれる政策も導入されます。こうした状況は、日本経済が長期的な低迷に陥っていく過程の一断面であるといってよいでしょう。
EL:新しい状況へ対応する過程で、まるで吸い込まれるように「金融システムの機能不全」という穴へ落ちてしまったんですね。背筋が寒くなるようなお話です。
齊藤先生:こうした、一見妥当と思われる意図に基づいて取り組まれたことが、意図せざる結果をもたらして、経済に大きな打撃をもたらしてしまう、というような事例は、今日の私たちも学ぶ意義が大きいように思います。
現代の日本経済が持つ課題
EL:ここからは、現代の日本経済に目を向けてお話を伺っていきたいと思います。
これまでに見てきた経済史の延長線上に現在があると思いますが、現代日本の経済が置かれている状況、そして抱えている課題にはどのようなものがあるのでしょうか?
齊藤先生:現代の日本経済の課題は、1990年代以降に明らかになってきた新たな競争環境に、日本人の多く、日本企業の多く、そして日本政府が十分に対応できていないこと、だと思います(私自身を含めて、です。自戒しております)。
1980年代を迎える頃までの日本は、いわばキャッチアップ段階で、欧米先進国に参考にすべき対象が多く存在しました。そうした段階の経済においては、目標も明確で、実現すべきことも見えていますので、それに向けて着実に近づいていくことが重要になります。例えば、コンピュータ産業ではIBMという明確な目標が存在し、IBMと同様なことができるようになれば、それが成功だ、ということが明確です。
EL:明治以降、日本は欧米の先進国に対して「追いつけ追い越せ」の精神で成長してきたと思うので、キャッチアップ的な発想の方が慣れていたのかもしれませんね。
齊藤先生:しかし、技術水準が向上して、多くの分野で世界トップレベルに近づくとともに、サービス産業化やIT化が進み、アイデアにより新たなサービスを生み出すことが重視される世の中になれば、キャッチアップ型の発想で成功することは困難でしょう。むしろ、新たなサービスを発想できたり、誰も取り組んでこなかったビジネスモデルを実行したり、といったことを果敢に実現していく人、企業が求められることになります。
現状を踏まえれば、当たり前の主張かもしれませんが、時代背景によっては全く別の能力が求められる、というように、相対化して理解した方がよいと思います。時間が経過すれば、また別の能力が求められるようになるでしょう。
EL:キャッチアップ型の発想が必ずしも悪というわけではなく、時代背景が変化する中で求められる能力が変わってきたんですね。それにしても、世の中が急激に変わっていくなかで、それに柔軟に対応するのは容易なことではないと思います。
齊藤先生:そうですね。例えば、当然ながら、競争力がない事業を抱えた企業は、その事業から速やかに撤退することも求められるようになりますが、これは従来の日本的な経営が苦手としてきたところでもあります。
1990年代に日本企業の相当数が競争力を低下させたのは、バブル崩壊の打撃だけではなく、こうした長期的な変化による面がある、という視点で捉える必要があるでしょう。
ある時期までの日本は成長性に富んでいて、既存のビジネスが成功していく可能性が高い時代だった。しかし近年では、失敗したらすぐに撤退しないといけない、自社に成功するプロジェクトと経営資源があるなら、他の企業に遅れを取らないように一分一秒でも早く着手しなければいけない、そんな時代になっています。
途上国からは競争を仕掛けられ、先進国は得意なところだけに経営資源を集中して競争を仕掛けてくる。そうした中で、自分はどこだったら勝ち残れるか、どの分野ではもう撤退しなければいけないか、売却しなければいけないかということを、スピーディーに考えながら対応していく経済の仕組みになってきているんですね。
EL:新しい競争環境は、1980年代を迎えるまでの日本が置かれていた環境と大きく異なることがよくわかります。そうした新しい時代への対応として、どのような政策が行われてきたのでしょうか?
齊藤先生:経済政策の面では、過去に行われた公共事業による需要創出、ないしそれによる雇用創出を目的とした財政政策のように、需要下支えを重視した政策では効果を得づらいのは当然といえるかもしれません。1990年代後半から「構造改革」が叫ばれるようになり、近年では「成長戦略」という用語が盛んに用いられるようになりましたが、経済の仕組み自体を変える必要がある、という認識の現れでしょう。もちろん、財政赤字が深刻なので、という理由もありますが、経済のあり方が大きく変化したことに対応しています。
また教育の面では、1990年代に、発想力などを重視した「新学力観」という考え方が出てきたのも、そうした状況への対応であったといえるでしょう。
さらに金融システムの面からは、既存の取引先との継続的な取引を行うことが得意な、銀行中心の金融システムから、たくさんのプロジェクトの中から成功するプロジェクトを探し出すことが得意な、市場中心の金融システムへの変化も進んでいます。これは、米英的な金融システムとか、コーポレートガバナンスがあるべきだという想定が先行して変わっていた部分もあるのですが、先ほどお話ししたように、成熟段階にある日本がさらされている新しい競争環境への対応という点では、大きな歴史の流れの中に位置づけることができます。
このように、非常に大きな変化が進んできた、ないし、現在進行形で進みつつある、というのが近年の経済であり、私たちはそうした大きな変化を目撃してきた、目撃している、ということになるのだと思います。
歴史から何を学び、どう生かせば良いか
EL:ここまで、いくつかの事例をもとに、戦前〜現代の日本の経済史とその捉え方などについて教えていただきました。
最後はそれらを踏まえた上で、歴史を学ぶ意義や、歴史から何を学びどのように活かせば良いかということに目を向けてお話を伺っていきたいと思います。
齊藤先生:自分も歴史研究者ですので、過去のことに興味を持ってくださる方が世の中にたくさん出てきたとすれば、もちろんそれは嬉しい思いが強いわけですが、ただ、過去に対する興味の持ち方は、本当に難しいんですよね。
例えば、過去のことを取り上げて評価するということは、よくあることだと思います。「あの時の政策はどうだった」とか、あるいは民間企業に勤めている人であれば「A社長のときのあの方針は適切ではなかった」とか、そうした話題になることは多いでしょう。
そのように過去のことを評価する際に、得てして評価する時点における評価基準で判断してしまう、別の言い方をすれば、現在の基準を暗黙裡に過去の出来事に対して押し付けてしまう、ということが行われているように感じます。もちろん現在の基準で過去を評価することによって見えてくるものもありますが、見えなくなってしまうものも多いと思います。
EL:先ほどのお話にあったバブル発生と崩壊にまつわる事例も、当時の状況を考慮して考えるべき例の一つですね。
齊藤先生:もし自分が、結果的に100兆円の不良債権を作り上げることに加担した一員だとして、その当時の状況を考えれば、銀行員の雇用を守らないといけないし、金融自由化で貸出先がなくなっているわけだし、潰れるわけには行かないとなった時に、不動産関連融資を行ったとしても全く不思議ではないと思うんです。
過去のことについて、その当時における状況という「文脈」に身を置いて考えてみることは、正確な評価をするうえで非常に重要であると思います。その際、「文脈」を正確に知ることは歴史を学ぶことの大きな意義の1つですし、また、「文脈」を踏まえた解釈をしようと努める姿勢を身に付けることも、歴史的な考え方に触れることの大きな効果であると思います。それにより、本当は関係があることを「関係ない」と捉えたり、関係がないにも関わらず「大いに関係がある」と解釈するようなことは減るのではないかと思います。
EL:ただ過去に起きた出来事だけを学び、その当時の時代背景といった文脈を無視して、現代の考え方だけで判断することは、正しい理解から遠ざかる危険があるということでしょうか。
齊藤先生:そうですね。当時の文脈を尊重しつつ、なんでこう変化してきたのかな?と考えて初めて過去を正確に認識でき、それをすることで、なぜ今はこうなっているのか?という理解につながると思います。
そして、今の状況というのは当然将来につながっていく。今日の次には明日があるし、今年の次には来年があるし、この10年の次には次の10年がある。
そうであるからこそ、現状をきちんと認識しようとすることは、将来への影響力があるのです。もちろん同時代での人間の認識能力には限界がありますから、認識しようと思っても認識できないことも多いと思います。それでも、虚心坦懐に考えようとしないと、見えることも見えてこなくなってしまうんですね。
EL:現代も、将来のある時点から見返せば歴史上の一場面になります。当然のことですが、過去の人々の行動が今の日本を作っているように、今の私たちの行動が将来の日本を作っていくわけですよね。
歴史を学ぶ意義や、歴史的な考え方を持つことの意義は、今が今だけではなく将来へつながっていくという、当たり前のことを改めて気付かせてくれることなのかもしれません。
齊藤先生:過去を見ていくと、その時の世の中を認識しながらも、自分の既得権益を守ろうとしてしまった人たちもいるわけです。
「これだけ財政悪化しているなら、もっと早く経済に余裕がある段階で増税しといてよ」って、若い人の立場なら思うかもしれません。消費税は1989年になって導入されますけど、実はその十数年前に消費税的なものを導入しようという動きってあるんですよね。
1970年代、この当時にはすでに高齢化も進んできて、高度成長が終わってみんな将来に不安を持つようになったから福祉を求めるようになって、では社会保障を拡充しましょう、ということになるわけですが、そのままだと財政赤字になるわけです。
一過性の不況が原因ではなくて構造的な要因で発生している赤字に対し、構造的な歳入をもって対応するのが常道だとなったら、税金しかないわけですが、でもいざそれが発表されたら、世論調査でボコボコにされて、とてもじゃないけれどこんな公約を掲げて選挙戦を戦えませんということになって取り下げてしまうんです。
その主張を簡単に取り下げたのは政治家の無責任といえるかもしれません。しかし、「税金を払いたくない」という気持ちのために、当時の状況を判断しながらも、消費税の導入を拒んだ当時の有権者の判断は本当に正しかったのかという議論が出てきてもおかしくはないでしょう。
EL:耳の痛い話ですね…。目の前の生活はもちろん大事ですが、そのために歴史的な考え方を失って後の世代に負担を先送りするなら、それが本当に正しい判断かは疑問が残ります。
齊藤先生:過去から未来への文脈の中で、現代はどうなのかということを相対化して捉えるには、歴史的な視点というのも欠かすことができないんですね。
バブルと似たようなことは、今後起きてもおかしくはない。では今どうすればいいんですか?となった時に、事実は正確に認識できるようにアンテナを張る。それを理解するために経済学とか経営学とか政治学が必要なら、学んでみても良いと思います。
歴史研究者としては、現状をきちんと認識しようとしている人がたくさんいるか?、ということは、将来に影響を与えると思うのです。
まとめ
今回は、経済史・経営史がご専門のフェリス女学院大学齊藤直教授に、バブル崩壊前後の日本経済史を通じて、今私たちが歴史から学べることについて教えていただきました。
その時の社会背景など、当時の文脈に身を置いて歴史を振り返ることは、その出来事を評価するために必要な姿勢であり、さらにはその延長線上にある現代への理解にもつながります。そしてそれは、過去から未来へ向かう歴史の中で、現代を相対化して捉える上でも重要な視点である、というお話でした。
過去の経済史に残るような重大な出来事は、今後の日本で再び起きないとはいえません。そうなった時に私たちが現状をどのように判断し行動するのかによって、新しい歴史が作られていくといえるでしょう。
(取材・執筆・編集/エモーショナルリンク合同会社)