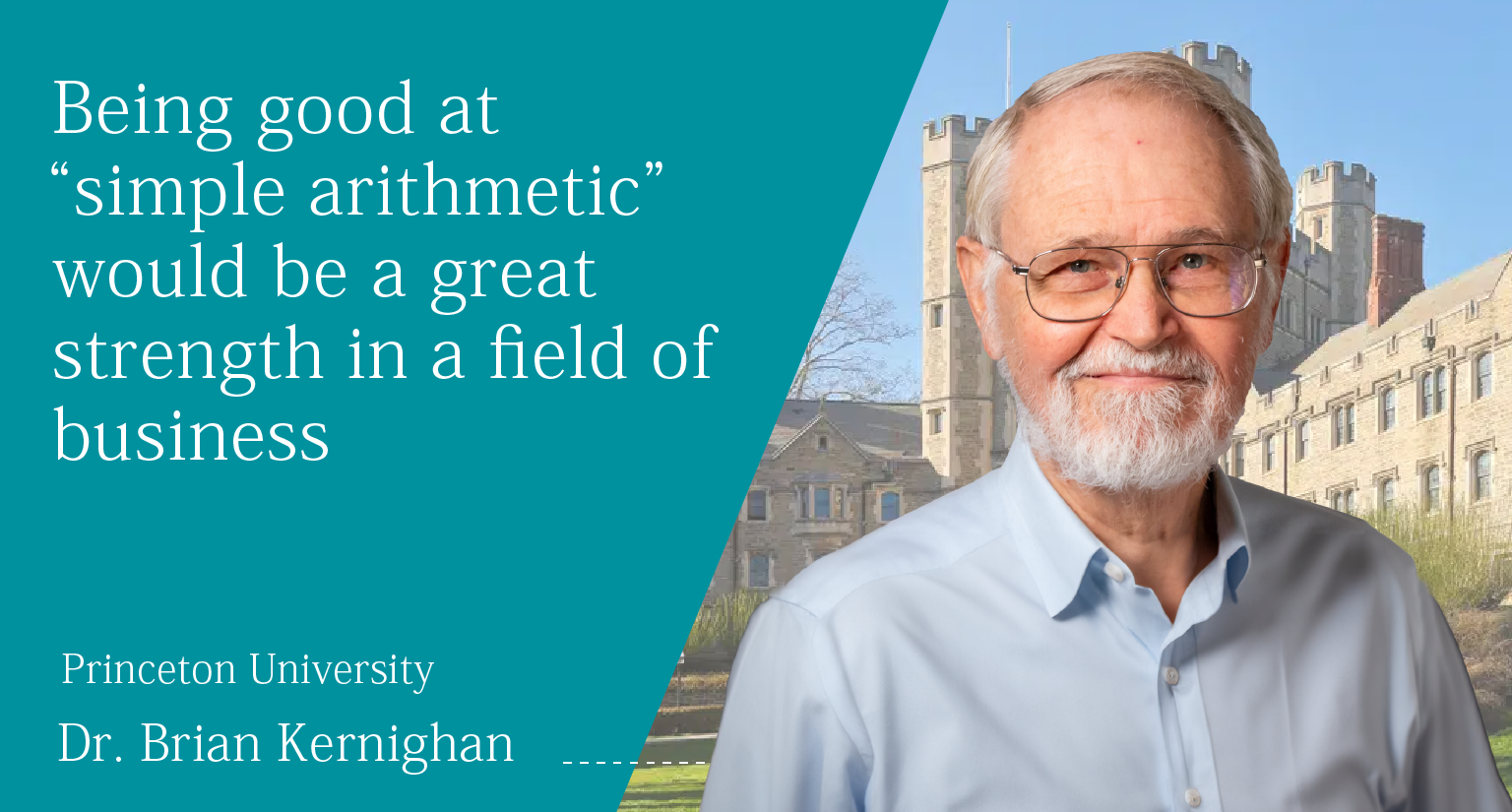昨今、テクノロジーの進歩はますます加速しています。
それに伴い、障害者の方や病気の方を補助するような技術も発展してきているものの、ミスマッチな開発が行われてしまっているケースも存在します。SDGsも踏まえ、そういった方々の社会進出をサポートするには、テクノロジーと身体とをつなぐ視点が欠かせません。
そこで今回は、『体はゆく できるを科学する〈テクノロジー×身体〉』の著者である、東京工業大学の伊藤教授にインタビューしました!

取材にご協力頂いた方
東京工業大学 科学技術創成研究院 未来の人類研究センター長
東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 教授
伊藤 亜紗(いとう あさ)
MIT客員研究員(2019)。専門は美学、現代アート。もともと生物学者を目指していたが、大学3年次より文転。2010年に東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻美学芸術学専門分野博士課程を単位取得のうえ退学。同年、博士号を取得(文学)。
主な著作に『体はゆく できるを科学する〈テクノロジー×身体〉』(文藝春秋)、『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)、『手の倫理』(講談社)などがある。
WIRED Audi INNOVATION AWARD 2017、第13回(池田晶子記念)わたくし、つまりNobody賞、第42回サントリー学芸賞、第19回日本学術振興会賞受賞。
「できる」かどうかは他者との比較で全て決まるものではない

佐藤:伊藤先生の著書『体はゆく できるを科学する〈テクノロジー×身体〉』では、非常に新鮮な切り口で「できる」について取り上げられています。書籍の中にあるようなテクノロジーの活用は、今後注視していくべき分野かと思いますが、伊藤先生が着目されたきっかけはどのようなものだったのでしょうか?
伊藤教授:私は普段、「できない」ことの研究をしています。障害や病気がある方の身体というのは自分とは全然違って、視覚障害がある方は視覚がない前提で世界を見ていらっしゃいます。なので身体の使い方はもちろん、使ってる情報も、世界のイメージも違うわけです。自分はたまたまこの身体を持って生まれたので、この身体としてしか世界を経験できませんが、実際には違う身体だからこそ見えてくる世界の顔があるんです。そういうものを当事者の方に直接インタビューして、私が文章にまとめるという仕事をしています。
やはり従来の学問だと、理系も人文社会系も人間の身体を一般化して語るんですが、そうやって一般化できない部分って実はたくさんあると思うんですね。もちろん、障害や病気がもたらす困難もありますが、その困難を通じて発見される身体の可能性もあります。一方で、その身体ならではのことをアカデミックな場所に落とし込んでいかないと、スカスカの身体をベースに世界中の学問が進んでいってしまう、と考えると結構危機感も持っています。そういう意味でも、「できない」ことはすごく面白いなと思って普段から研究しています。実は最初は「できる」ことってつまらないな、と感じていて、「できない」ことが面白いと思っていました。
佐藤:それは意外です。つまらないと感じていたことが「面白い」に転じたのはなぜだったのでしょうか?
伊藤教授:2017年に、理工系の研究者の方々との共同研究に加わることになったんです。脳科学や情報科学の様々な研究者が集まって、技能獲得の仕組みとそれをサポートするようなテクノロジーの開発を行うというものです。扱うものも音楽からスポーツ、病気まで多種多様で、5年やっていく中で「できる」も面白いな、と感じ始めました。
一般的には「できる」のは良いことだと思われていますし、みんな「できる」ようになりたいと思っていますよね。ですが、実際の社会では「できる」というのは数値的なものだったり、他者と比べたり、あるいは資格の有無といった、基準となるものとの比較が基本になっているところがあります。では、実際それが「できる」ようになった時、身体に何が起こっているか、についてはあまり注目されていません。
佐藤:確かに、こうして振り返ってみると「できる」ことの定義は非常に曖昧ですね。
身体が意識を飛び越えていく瞬間が「できる」ようになるということ
伊藤教授:私は誰かよりも「できる」という競争的な意味で捉えることが、実感や身体的な経験としての「できる」を感じにくくしてしまっているのではないか、と思うんです。身体的な経験とは何か、というと自分の意識と身体について考えた時、普通は意識が身体をコントロールしていると考えますよね。ただそれだと、新しいことって絶対にできるようにはならないんです。「できない」ことは意識からするとうまくイメージできないので、例えばスケートの3回転半ジャンプをやったことがないのに、映像を見ても自分の中で感覚は再現できません。だから身体にうまく命令を出せなくて、「できない」わけです。そして、そもそもなぜイメージが作れないかといえば、身体がそれをやらないからなんですよね。そうすると、意識も身体も困ったことになります。
じゃあ、どうやったら新しいことが「できる」ようになるのかと考えると、身体が意識を超えて、意識が経験したことのない領域へと先に行く瞬間があるんです。一般的な、能力主義的な「できる」というのは、なんとか努力して頑張って身体を制御し、レベルアップしていくものだと思われています。確かにその要素もありますが、本当に最後の「できる」ようになる瞬間は、意識を身体が追い越していくような状況になっているわけです。
佐藤:なるほど。伊藤先生のお話を伺っていると、「できる」ことについて考える楽しさが伝わってきます。読者の方も「できる」がどのような感覚か気になるところかと思うのですが、実際に、私たちが「できる」ことを体験する身近な機会はあるのでしょうか?
伊藤教授:「できる」ことを体験する場としては、いわゆる新しいテクノロジーを体験したい場合はミュージアムや展示会などで体験できます。ただ、身体が新しく「できる」ことを体験するという意味では、意外と身近なところでもできたりしますね。
私は先日、初めて自転車のフィッティングに行ってきたんです。フィッティングって私も知らなかったんですが、ロードバイクのような本格的に自転車の可能性を追求するレベルになると、自転車は乗る人の身体に合わせてものすごく微調整をしなければならないそうです。そして、乗る人としても自転車に合ったこぎ方を見つけなければいけなくて、やってみたらかなり面白い体験でした。テクノロジーと身体がうまく組み合わさった時に見つかる意外な可能性、と考えると、フィッティングも私の研究と重なることがあります。
フィッターの方が仰るには、まず座るとはどういうことかが非常に大切で、ロードバイク用のサドルが痛い人はきちんと座れていないんだそうです。サドルの高さを数ミリ変えるだけで姿勢が全く変わるし、気持ちも上向きになるんですね。良い姿勢にピタッとはまった時というのは遠くの景色が見えるし、自信がついて堂々とした気持ちになれます。自転車という道具と身体がフィットしたことによって、足が自然と動いて自転車をこぎ始めるんです。
佐藤:それはまさしく、伊藤先生の研究されている「できる」体験ですね。フィッティングの際には、フィッターさんの感覚のみの調整になるのでしょうか?
伊藤教授:フィッティングする時にも、一応数字は使っています。関節が何度くらいになっているとか、脚首は何度になっているとか、そこから何度くらいにするとベストか、といった数字の手がかりはあるんです。ただ、フィッターさんは数字の示す正解に対して、乗り手がここなら気持ち良い、ここならしっくりくる、という感覚とをうまく擦り合わせていくことをお仕事とされています。言い方を変えれば、テクノロジーと人間をつなぐお仕事ですね。
座るということ一つ取っても、私たちは「できる」と思っていますが、実は「できない」ことがまだまだあります。しかも、実はできていないことを探すにも、多くの人はいつもやっているやり方をしてしまう。では、いつもと違う方法にどうやったらたどり着けるか、と考えた時に身体をうまく導いてくれるのがテクノロジーなんです。
健常者の視点だけで正解を考えても最適解にはたどり着けない
佐藤:時にはテクノロジーだけが独り歩きをしてしまうようなケースもありますが、伊藤先生が『体はゆく できるを科学する〈テクノロジー×身体〉』で取り上げられている事例は、フィッティングと同様うまくフィットした成功事例といえそうですね。
伊藤教授:私は東工大に在籍しているので、周りの人は技術屋さんばかりですが、技術は作っているだけでは意味がないということは当然皆さんわかっています。例えば『体はゆく できるを科学する〈テクノロジー×身体〉』の書籍で最初に取り上げさせて頂いた古屋さんは、ピアノの研究をされている方です。といっても道具を作って終わり、ではなくて中学生、高校生向けにトップレベルのスクールを運営していたり、ほかにも手の動きをデータ化して本人が確認できるようにするなど、手厚くピアニストのケアをしているんです。
特に、ピアノの先生が言うことって、すごく人文的というか、感覚的になることがありますよね。「ピアノの大きさをちゃんと感じなさい」とか、そういう表現は伝統的に使われている ”きっかけ” を作るための言葉だったとしても、やはり「できない」人には伝わりにくい。だからこそ、テクノロジーとピアニストとをきちんとつなぐ存在が必要なわけです。古屋さんはその部分をすごく丁寧にやっていて、先生が言っていたこの感覚は数字でいうとこうだよ、と本人の実感として落としていくお仕事をされています。
書籍の後半で紹介している牛場さんの脳卒中の研究でも、彼自身が患者さんと関わりながらその方の身体に合った機械の修正や、本人の実感として納得できるようにつなぐことの重要性を仰っています。テクノロジーの開発者は、古屋さんや牛場さんのように現場の使用者に寄り添った姿勢を持つことが大切だと思いますね。
佐藤:現場の使用者に寄り添うことを考える際に、注意すべき点などはあるのでしょうか?
伊藤教授:大切なのは、「できる」ということを健常者の視点で定義しないことです。例えば、視覚障害者の方向けに何か製品を作ろうと思うと、視覚情報が手に入れられないなら触覚に置き換えて触れるタブレットを作ろう、と考えたりしますよね。ですが、当の視覚障害を持っている方々からすると、そんなのいらないんです。普段から視覚なしで世界を認識できているのに、余計な情報を持ってこられても意味がないし、もっというと邪魔なんですよ。なので、開発者側が健常者の得ている情報を正解だと思い込んで、障害部分を補完するような考え方をすると全く見当違いの製品になってしまいます。元気な人や健常者を基準にするとずれてしまうので、やはり実際に当事者の人たちが「こういうことができるようになりたい」と思っていることを考えるのが大事です。
そういう意味でもテクノロジー自体の多様性は非常に重要だと思います。義手ひとつとったって、先天的に腕がないような人は、義手みたいな変なものを着けても邪魔になってしまう。だから、まずは正解を勝手に決めつけないでスタートすることが求められるんです。
そうやって開発を進めていくと、健常者だと気づかないような開発の方向性が見えてくることもあります。なので、テクノロジー開発の現場にも多様性を組み込んでいくと、新しいイノベーションのきっかけにもなると思います。例えば、曲がるストローはもともと真っ直ぐなストローだと飲めないような、障害者の方向けに開発されたものでした。今ではそれが一般にも浸透しているので、障害者の方の視点を取り入れた製品だからといって、必ずしも障害者の方専用になるとは限らないわけですよね。一方で最近では環境問題を考慮してプラスチックストローがどんどん減ってきていて、障害者の方々が困るといったことも起きているので、どこが正解になるのかは常に考えていく必要があるでしょう。
障害者雇用の促進が新たなイノベーションの創出につながる
佐藤:大変興味深いお話なのですが、例えば企業として障害をお持ちの方々の雇用枠を作り、商品開発に参加していただくことで、イノベーションが促される可能性は考えられるのでしょうか?
伊藤教授:それはもちろん考えられますし、どんどんやっていただきたいですね。障害者の方全員がクリエイティブでなければならない、ということではなく、技術開発に参加したいという想いをお持ちの障害者の方はたくさんいらっしゃいます。それこそGoogleでは視覚障害者の方も働いていて、ボイスオーバーなどの読み上げ機能は社内に当事者がいたからこそ生まれたものです。ただ、日本だと法律で障害者枠を作って雇用しなければならないから、というだけで彼らの持っている知識や経験を開発にうまくつなげられていないケースが多いと思います。
そこをうまくつなげることが、今後は重要な作業になってくるのではないでしょうか。興味があれば、Sight Tech Globalのように、Googleやマイクロソフトといったジャイアントテックがお金を出して、視覚障害者の方々にまつわる研究発表をするカンファレンスもあります。障害者の方々を助けてあげよう、と考えるのではなく、一緒にやっていく仲間として対等に捉えるとお互いにWinWinな関係が築けるはずです。
佐藤:障害者雇用という、SDGsに貢献しながらイノベーションを生み出せる可能性が高くなるのは、起業家や企業経営者にとっては見逃せない要素となりそうですね。新商品開発や新サービスを考える上で、事例などがあればぜひお伺いしたいです。
伊藤教授:直接的にビジネスに関わることではありませんが、『見えないスポーツ図鑑』という書籍で行った取り組みは様々なところから好評を得ているので、参考になるかもしれません。スポーツって一般に目で見て「観戦」するものですよね。でも視覚的に得た情報は、実際に選手がその種目をプレイしているときの感覚と必ずしも同じとは限らない。そもそも選手はそんなに視覚を使っているわけではないですからね。そこで視覚障害者の視点を借りて、非視覚的な情報、つまり、選手がその種目を実際にやっているときの感覚に注目し、それを100円ショップで売っているような身近な道具を使って「翻訳」することを試みたんです。例えばフェンシングだと、視覚的には剣を持った人が突き合っているように見えますが、選手の実感は全く違うものでした。フェンシングは攻撃側と防御側が瞬時に切り換わるのが面白いところで、それには手首の柔軟な動きも必要になるということだったんです。
なので、その感覚を再現するために百円均一などで売っているアルファベットの形のパーツを使い、それらを知恵の輪のように組み合わせました。2人がそれぞれ両端を持って目をつぶり、1人はそれを外そうとしてもう1人は外されまいと動くんです。そうすると、パーツを外すためには相手の動きにうまくついていってスッとかわすような動作が必要で、それがすごくフェンシングに近いと選手の方が教えてくださいました。こうした翻訳を、これまでに12種目の競技について行っています。
こうやって翻訳を入れれば、種目そのものをすぐにできるようにならなくても、感覚はわかりますよね。遊びとして小学生のうちに経験しておくだけでも、将来フェンシングをやってみた時にスタートしやすくなるんじゃないかと思います。ちなみに、一番感謝されたのは応援団の人たちからでした。応援団っていろいろなスポーツの応援に行かなければいけませんが、やはりルールが頭に入っていても心から応援はしにくいんですね。でも、翻訳によって選手が何を頑張っているのかを理解することで、手っ取り早くわかるようになったと言われました。
佐藤:それは大変面白い試みですね。「できない」ことを「できる」ようにする過程を追求していけば、今後も様々な新しい発見がありそうです。
伊藤教授:見た目の類似性ではなく感覚の類似性で翻訳することで、教育の現場やスポーツ観戦などでの解像度を上げる目的も目指せるかなと感じています。最初こそ視覚障害者の方にスポーツを翻訳するところがスタートでしたが、今では視覚障害者の方に限らず健常者にとっても新しい技術を手に入れるための大きなヒントになっているわけです。なので、そういう視点が教育や、先ほどご紹介したフィッターのような人につながっていくと、さらに良い発見があるのではないかな、と思います。
「できない」ことが「できる」ようになるメカニズムは、まだまだ完璧には解明されていません。
だからこそテクノロジーの活用には大きな可能性があり、人とテクノロジーをつなぐ存在も重要になってきています。
特に、障害者雇用の促進やそこから生まれるイノベーションについては、ビジネスチャンスも感じられます。起業家や企業経営者の立場としては、今後見逃せない分野となっていきそうですね。
関連書籍
(対談/佐藤 直人)