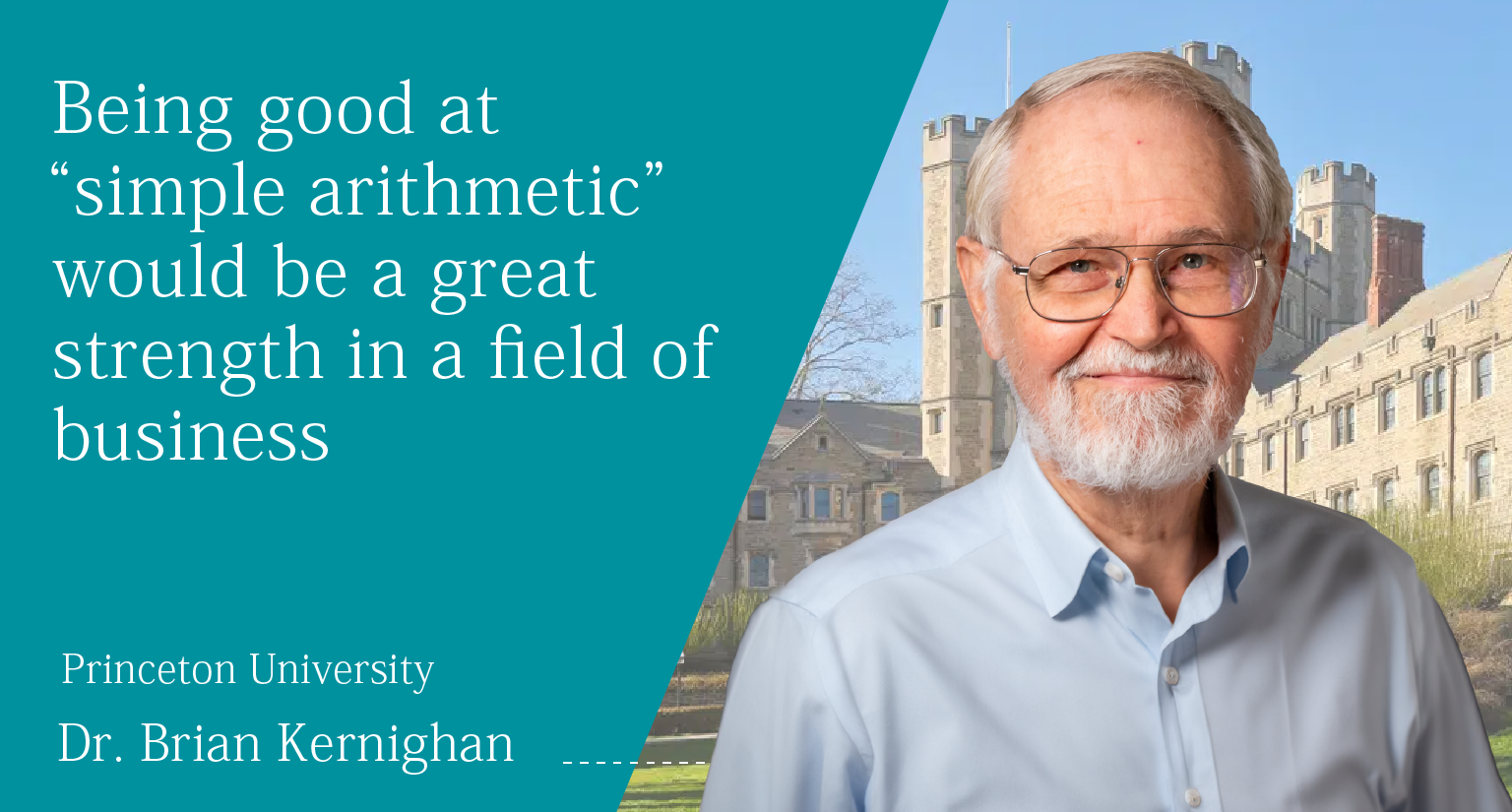世界は2050年のカーボンニュートラル実現のため、太陽光発電や風力発電など、様々な技術開発を進めています。
国を挙げての取り組みとなるカーボンニュートラル関連の事業は、今後、企業にとっても大きなビジネスチャンスとなっていくでしょう。
そこで今回は、カーボンニュートラルの実現に向けて精力的に活動されている東京大学の松本真由美先生にインタビューしました!

取材にご協力頂いた方
東京大学 教養学部附属教養教育高度化機構 客員准教授
松本 真由美(まつもと まゆみ)
上智大学外国語学部卒業。大学在学中からTV朝日の報道番組で取材活動を行い、その後、NHK BS1でワールドニュースキャスターを6年間務めた。環境NPO活動をきっかけに、2008年5月より研究員として東京大学での環境・エネルギー分野の人材育成プロジェクトに携わり、2013年4月より現職。現在は教養学部での学生への教育活動の一方、講演、シンポジウム、執筆などの活動を行う。総合資源エネルギー調査会「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」等、政府の審議会等の委員も務める。
専門は、環境・エネルギー政策論、科学コミュニケーション。研究テーマは、「エネルギーと地域社会との共存」、「環境・エネルギー政策の国際比較」「企業の環境経営動向」等、環境とエネルギーの視点から持続可能な社会のあり方を追求する。
カーボンニュートラルとは「温室効果ガスの排出量を差し引きゼロにする」こと

佐藤:それでは最初に、カーボンニュートラルとは何か、教えていただけますか?
松本先生:カーボンニュートラル(carbon neutral)とは、人間活動によって排出される二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスを、植林、森林管理等で吸収・除去することで、排出量をプラスマイナスゼロにすることを意味します。人間活動により大気中に排出された二酸化炭素のおよそ半分は、陸上の生態系や海洋が吸収してくれます。しかし、約半分は植林などによって吸収する必要があります。日本やEU(欧州連合)、米国は、温室効果ガスの排出を2050年までに実質ゼロを目指しています。
ちなみに、温室効果ガスの中での割合が多く、地球温暖化の最たる原因である二酸化炭素の排出量を実質ゼロの状態にすることも、カーボンニュートラルと言われます。中国の目標は、2060年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすることです。
どちらもカーボンニュートラルに相違なく、温室効果ガスの中では、二酸化炭素の割合が多いことを考えると、二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすることは非常に重要といえます。
佐藤:温室効果ガスによる地球温暖化の進行が問題視されるようになってから、すでに相当の年月が経過していますが、このまま地球温暖化が進んだ場合どのような悪影響が考えられるのでしょうか?
松本先生:地球温暖化が進んだ場合の悪影響として考えられるのは、まず気温上昇によって大気中の水蒸気量が増え、大雨が降りやすくなることです。その他、地球温暖化による海面水位の上昇や熱波、干ばつ、洪水といった気象災害・異常気象の頻度と規模の拡大が懸念されます。特に途上国は、先進国と比べてより大きな被害を受けることが懸念されます。
IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)によると、1995年〜2014年を基準とした場合、気温上昇が最も低いシナリオでも2100年には世界平均海面水位が28〜55cm上昇すると予測してます。最も高いシナリオだと、63cm〜1.01mもの上昇です。また、世界の平均気温は1850〜1900年と比べ、2020年時点ですでに約1.1度上昇したことを発表しています。もしこのまま私たちが何も対策をしなければ、今世紀末には平均気温が約4度上昇すると予想されています。何も対策を行わなければ、大災害が避けられない未来になってしまうでしょう。
佐藤:やはり、世界で一丸となって取り組まなければならない問題なのですね。
松本先生:その通りです。2021年11月時点では、154ヵ国・1地域が、2050年までにカーボンニュートラルを実現することを表明しています。これらの国におけるCO2排出量は、世界全体に占める割合の約4割にのぼります。世界最大のエネルギー起源CO2排出国(29.4%/2019年)である中国も、2060年までにカーボンニュートラルを実現することを、2020年9月の国連総会で習近平国家主席が表明しました。カーボンニュートラルの実現に向けて、世界全体が動いているのです。
佐藤:その中で、日本はどのような取り組みを行っているのでしょうか?
松本先生:脱炭素化における日本の施策の方向性は、まず徹底的な省エネルギーの活用を行い、温室効果ガスを排出するエネルギーの使用量を減らすというものです。そこで重要になるのが、高効率な省エネ機器の活用やエネルギー転換投資です。エネルギー転換投資の内訳としては、再生可能エネルギー、交通・輸送の電化、水素エネルギーの活用、そしてCCSなどがあります。CCSは、「Carbon dioxide Capture and Storage」の略で、二酸化炭素回収・貯留技術です。発電所や化学工場などから排出された二酸化炭素を他の気体から分離して集め、地中深くに貯留・圧入するというものです。
温室効果ガスは工業活動だけでなく家庭からも排出されるので、排出量そのものをゼロへと近づけていくことは難しいです。そこで除去技術であったり、省エネルギーの利用による温室効果ガスの排出量減少、あるいは森林や海洋などでの吸収などを合わせ、差し引きゼロを目指すという両輪での対策となります。除去の方法としては、大気中から直接二酸化炭素を回収し貯留する技術「DACCS」や、バイオマスエネルギー利用時の燃焼により発生した二酸化炭素を回収・貯留する技術「BECCS」といったネガティブエミッション技術を活用することが考えられています。
太陽光発電だけでなく洋上風力発電の導入も進められている
佐藤:再生可能エネルギーというと、日本は太陽光発電において、世界第3位の導入量となっていますね。
松本先生:はい。太陽電池技術というのは、もともと日本の誇る技術です。しかし、世界の太陽光発電市場では、IEA(国際エネルギー機関)が2022年8月に発表したレポートによると、中国企業の世界シェアは8割を超えています。
日本に目を移すと、太陽光パネルの国内出荷は減少しており、日系メーカーの輸入を含めて海外からの輸入は増加しており、今では8割が海外生産になっています。多くの中国製品も輸入されていると思います。総じて、国内の需要における日系メーカーの比率は減少していますが、住宅用では7割程度のシェアは維持しているようです。
太陽光発電の導入を進めていく上での日本の課題として、野立ての太陽光発電システムが全国的に広がったことで、別荘地の前に太陽光発電所が設置されるなど、地域紛争が各地で起きているという問題があります。全国の自治体の約1割が再生可能エネルギー導入に関する条例を制定しており、今後、立地制約によって野立ての太陽光発電所を大規模に展開することは難しくなるでしょう。
そのため今後、政府は屋根置きタイプの太陽光発電に補助金を出して推進していく方針です。加えて、「グリーンイノベーション基金」の中で498億円を投資し、次世代型太陽電池の開発にも力を入れています。「ペロブスカイト太陽電池」というもので、フィルム状に形成されるため軽くて曲がります。既存の技術では太陽電池を設置できなかった場所(耐荷重の小さい工場の屋根やビル壁面など)にも設置でき、建物の窓や自動車の曲面などにも塗布技術で作製することができます。現在開発されているペロブスカイト太陽電池には、フィルム型、ガラス型などいくつかのタイプがあります。ペロブスカイト太陽電池は廉価な材料で構成され、塗布技術で大量生産できるため、製造コストが安価な上に、2030年代中盤から大量の太陽光パネルの廃棄が懸念される中で、廃棄量を大幅に減らせることも期待されています。しかし大容量化や耐久性などの問題が残っており、まだ実用化されておらず、今は各国が競ってペロブスカイト太陽電池の開発を進めている状況ですね。
佐藤:なるほど。再生可能エネルギーとしては風力発電も有名ですが、日本だと太陽光発電ほどは導入が進んでいないイメージがあります。実際のところはどうなのでしょうか?
松本先生:風力発電については、陸上風力は中国が牽引し、洋上風力は欧州が牽引している状況ではありますが、日本でも洋上風力発電を脱炭素の切り札と位置づけ、動き出しています。日本における風力発電の電源割合は、2020年度は0.9%でしたが、2030年に5%が目標です。
世界全体で見ると、風力発電では陸上風力の方が導入量としては大きいですが、土地の立地制約の関係で海上への導入も進んできています。先に欧州の事情をお話しすると、洋上風力発電が導入され始めたのは、まず洋上の方が障害物がなく、風況に恵まれた環境で発電効率が高いという点が挙げられます。加えて、洋上は大規模に展開できるため大型風車の導入が可能なこと、そして制度面ではゾーニング、気象・海象の調査、漁業団体や環境団体などの調整を、政府が進めた後に発電事業者を公募する「セントラル方式」を採用しています。こうした方式によって発電事業者が事業に集中できる点も、洋上風力発電が発展した要因の一つだと思います。欧州は平坦な海域が40メートルほど広がっている場所もあり、海底に基礎を打つ着床式風力発電を展開しやすかったこともあると思います。
日本の場合、沿岸は水深50〜200mの広大な大陸棚に囲まれ、急に水深が深くなる地形です。政府が定めた促進区域(2023年1月時点で8区域)でも着床式の洋上風力発電を中心に進められることになりますが、長崎県五島市沖では浮体式の洋上風力発電の計画が進められています。洋上風力発電は、発電設備を構成する部品点数が数万点と多く、経済波及効果も大きいですが、産業界は、構成部品の国内調達比率を2040年までに60%にすることを目指しており、政府は補助金や税制などによる設備投資の支援を行う計画です。
佐藤:洋上風力発電がそこまで本格的に進んでいるとは知りませんでした。陸上という制約がなくなれば、これまで以上に再生可能エネルギーの大規模展開が近づきそうですね。
松本先生:はい。それに、洋上風力発電の導入には、
- 発電時にCO2を排出しない
- 経済性の確保
- 地元産業への好影響
などの意義があります。第6次エネルギー基本計画では、2030年度時点の電源構成として石炭やLNG、石油の利用を計35%削減する方針を掲げており、洋上風力発電をはじめ再生可能エネルギーの必要性が高まっているといえるでしょう。
特に、洋上風力だと発電設備の設置・維持管理に地元の港湾を活用するため地元産業の活性化や雇用の創出が期待できますし、発電設備を構成する部品数が多いことから、欧州では事業規模が数千億円に達するものもあります。こうしたことを考えると、地元産業を含めた関連産業(風力発電関連メーカー、建設・運転・保守点検など)への波及効果は非常に大きいものです。政府は洋上風力発電について年間100万kW程度の区域指定を10年継続し、2030年までに1000万kW、2040年までに浮体式も含む3000万kW~4500万kWの案件を形成することを目標として掲げています。
佐藤:となると、今後は洋上風力発電が日本における再生可能エネルギーの中心的存在となっていくのでしょうか?
松本先生:業界全体として、以前よりも活発な動きは見られるようになってきていますね。
とはいえ、再エネ海域利用法に基づく促進区域として指定されているのは、現時点では8区域で、動き出したばかりです。私が法定協議会で関わっている秋田県の「能代市沖・三種町・男鹿市沖」「由利本荘市沖」、そして「千葉県銚子市沖」、「長崎県五島市沖」の4海域の工事開始予定は時期が異なりますが、2022~2026年を予定しています。
例えば秋田県の由利本荘市と、能代市沖・三種町・男鹿市沖では、事業者の三菱商事がエネコという欧州の洋上風力発電を手掛けていた事業者を買収しており、欧州での洋上風力発電のノウハウや知見を取り込みながら日本の海域に合った洋上風力発電を展開していく方針です。この話は、法定協議会の場でオフショアウィンド合同会社のリーダーの方からお聞きしました。また、東京電力リニューアブルパワーも洋上風力発電を国内外で展開していくために、イギリスの浮体式洋上風車の事業者を買収しています。
日本では今、様々な企業が洋上風力プロジェクトに参入を試みていますが、これまで洋上風力発電を手掛けた経験がない企業は、電力会社や商社、建設会社といったそれぞれの強みを持った会社と連携してコンソーシアムを形成しています。
佐藤:一部の企業はすでに洋上風力発電の可能性を見出し、動き始めているのですね。
松本先生:はい。ただ、再生可能エネルギーであってもやはり反対の意見は出てくるということは、事業として参入する際には注意すべきだと思います。今でこそ太陽光発電の施設を建てる際には政府の規制もあり、立地条件など厳しい制約が課されています。しかし、2012年7月に再生可能エネルギーの固定価格買取制度がスタートした当時はそこまで厳しい制約はありませんでした。住民との合意形成や説明会なども満足に行われていなかった時期は、やはりトラブルも多発していました。その後、厳しい制約が課されるようになってからも反対意見は一定数あるので、今後も地域に受け入れてもらうという意識は重要ですね。例えば、秋田県の洋上風力発電の促進区域においても、漁業者や住民の方に還元するための市民サービスを、発電事業者の方に実施していただいています。
事業として再生可能エネルギーを手掛けて、事業者が収入を得て終わり、では理解は得られません。やはり、いかに地域に還元するか、地元の企業を活用して地域活性化に貢献するか、というビジョンを示すことができないと住民に受け入れてもらうことは難しいでしょう。これは今まさに政府が目指しているところとも重なっていて、洋上風力発電を地元と共生しながら日本の産業として発展させることが重要です。
EVや水素エネルギーの活用も世界から注目を集めている
佐藤:ここまで洋上風力発電の導入に向けた動きが本格化しているとなると、先ほどお話しいただいたエネルギー転換投資も、洋上風力発電が中心となっているのでしょうか?
松本先生:はい。エネルギー転換投資の投資額としては再生可能エネルギーが最も大きく、その中でも投資の割合が多いのは太陽光発電と風力発電(陸上・洋上)ですね。現在、世界的に見てもカーボンニュートラルの実現に向けて「エネルギー転換への投資」が加速しています。ちなみに、エネルギー転換投資のうち、再生可能エネルギーの次に大きな割合を占めているのが「交通・輸送の電化」で、EV、すなわち電気自動車や蓄電池への投資です。
佐藤:再生可能エネルギーに次いで、EVに対して注目が集まっているのはなぜなのでしょうか?
松本先生:EUをはじめ、世界中でEVに関連する施策が実施されていることが要因でしょう。EUでは、2017年10月に欧州バッテリーアライアンス(EBA)が設立されました。EUのバリューチェーンを構築し、競争力ある蓄電池産業を創出することを目指して、積極的に補助金を出しています。
また、アメリカのバイデン大統領は2021年8月、2030年までに新車販売(乗用車と小型トラック)の半数以上をEV、FCVとする大統領令に署名しました。2021年11月にはインフラ投資法案が下院で可決されましたが、2030年までに全米50万ヶ所で充電設備の設置が進められる予定です。2022年8月16日には「インフレ削減法」が成立し、再生可能エネルギーやグリーン水素、蓄電池などの気候変動対策やエネルギー安全保障への支援として10年間で50兆円を拠出する計画です。
中国では新車販売が回復し、EV販売も増加しています。2021年の新車の販売台数は前年比3.8%増の2627万超で4年ぶりにプラスに転じており、新エネルギー車(NEV:EV、PHV、FCVの3種類)の販売は352万1000台と前年比2.5倍の伸びを見せました。このうち、EVが290万台を占めています。
日本でも2022年8月31日に経済産業省で「蓄電池産業戦略」がまとめられ、日本の蓄電池の競争力強化を目指すことが示されました。車載用と定置用の蓄電池において、中国と韓国メーカーがシェアを拡大する一方、日本は近年縮小していることから、蓄電池産業の復活を図ります。
佐藤:世界的にEVへの関心が高まっている状況なのですね。自動車産業だと水素自動車も同様のカテゴリーかと思いますが、水素自動車への投資はそれほど取り上げられていないのでしょうか?
松本先生:EVの方が注目されているのは、水素自動車の最大のネックとなる、水素ステーションの整備を進めなければいけないという事情が関係してきますね。通常のガソリンスタンドの建設費が7〜8千万円と言われるところ、水素ステーションの建設費は、5〜6億円と言われており、コスト削減が不可欠です。水素自動車に乗る側としても、水素ステーションが各地になければ走行中に不安になってしまいますよね。そういう意味では、蓄電池を搭載するEVの方が普及しやすいのだと思います。
ただ、水素についてはコージェネレーション(熱電併給)システムに関連して、技術開発を進める動きが欧米でも活発化しています。現在、水素は脱炭素の新しいエネルギーとして世界的に注目されていて、再生可能エネルギー由来のグリーン水素の導入拡大が重要な脱炭素戦略に位置付けられています。
EC(欧州委員会)が発表した「2050年までの欧州水素ロードマップ」では、EU域内のエネルギー需要量の合計に対して水素が占める割合は2050年に成り行きで8%、野心的な目標では24%まで拡大するとされています。アメリカのバイデン政権も、2022年2月、グリーン水素ハブの開発に80億ドル、グリーン水素電解の研究開発に10億ドル、水素製造とリサイクルに5億ドルを投資すると発表しました。総額95億ドル(約1.1兆円)もの額を動かしていることを考えれば、水素の注目度が高いことは明白でしょう。
カーボンニュートラルには多くのビジネスチャンスが眠っている
佐藤:再生可能エネルギーは、研究開発によって進歩を続けているのですね。今後は国としてだけではなく、企業もいち事業者としてカーボンニュートラルの実現に向けた参入を検討することが増えるかと思います。その際には、どのようなビジネスが考えられるのでしょうか?
松本先生:日本が海外に比べて遅れている、つまりこれからのビジネスチャンスといえるものには、アグリゲーションビジネスやマイクログリッドが挙げられると思います。「アグリゲーションビジネス」とは、需要家側の再生可能エネルギーや蓄電池など小規模な分散電源をIoTを活用した高度なエネルギーマネジメント技術により、これらを束ね、遠隔・統合制御するサービスを提供するビジネスモデルです。アグリゲーターは電力の集中システムを設置し、エネルギー管理支援、電力売買、送電などのサービスを仲介し、需要家の電力需要を束ねて効果的にエネルギーマネジメントサービスを提供します。政府は2022年4月に、特定卸供給制度(アグリゲーターライセンス制度)を創設しました。2022年4月1日には、エナリス(東京都千代田区)が第1号のアグリゲーター届出事業者となり、再生可能エネルギーアグリゲーションサービスの提供を開始しています。これからアグリゲーターがさらに増えることを期待しています。
佐藤:エネルギー管理支援や電力売買というと、具体的にはどういったサービスを行うのでしょうか?
松本先生:例えば、工場等の大規模需要家の電源消費をアグリゲーターを通じて抑制するデマンドレスポンス(DR)が実用化されています。太陽光発電で大量に発電して余剰電力となったものを、デマンドレスポンスによって抑えたり、電力が足りないところに売却・供給する。そうやって、電力会社と工場などの需要家との間に立ってエネルギーの需給調整を行っているのがアグリゲーターです。今後はFIP制度(Feed-in Premium)の対象となる電源や家庭やオフィスなどの太陽光発電、EV、蓄電池、エネファームなど、多様な分散型電源を活用し、供給力等を提供するアグリゲーションビジネスの拡大が期待されています。
今では、PPA(Power Purchase Agreement:電力販売契約)という電力ビジネスモデルが広まってきています。発電事業者や小売事業者が自らアグリゲーターとして変動電源の予測・調整を行うこともできますが、アグリゲーターに委託するケースもあります。FIT(固定価格買取)制度に関わらない再生可能エネルギーの導入が進めば、やはり発電側から需要家に送るためにも受給調整が必要になりますから、アグリゲーターのニーズは非常に高まっているといえるでしょう。
ヨーロッパは10年ほど前からアグリゲーションビジネスが発展していて、導入拡大も積極的に進んでいます。しかし日本はここ1、2年の動きなので、今後本腰を入れて再生可能エネルギーの大量導入を行っていく際には、アグリゲーターの存在はますます重要になっていくのではないかと思います。
佐藤:なるほど。アグリゲーションビジネスと並ぶもうひとつのビジネスチャンスである「マイクログリッド」とはどのようなものなのでしょうか?
松本先生:マイクログリッド(小規模電力網)というのは、一定の地域において、すべての電力負荷を分散型電源から供給し、エネルギーを地産地消する仕組みのことです。各地域には太陽光発電や風力発電、蓄電池、ディーゼル発電機といった、「分散型電源」と呼ばれる小規模な電源が存在します。これらは平常時には送配電ネットワークとつながっているのですが、マイクログリッドでは、停電などの非常時の際には、送配電ネットワークから独立し、エリア内でエネルギーの自給自足を行うことができます。
日本ではマイクログリッドの運用は遅れている状況ですが、令和2年度から「地域マイクログリッド構築事業」の公募が行われているので、企業家の方は興味があれば事業として参入を検討してみてください。一人ひとりがカーボンニュートラルへの関心を高く持つことで、2050年の脱炭素社会実現に向けた動きはさらに加速していくはずです。
太陽光発電だけでなく、洋上風力発電や水素エネルギーの活用など、再生可能エネルギーの研究は日進月歩しています。
加えて、アグリゲーションビジネスやマイクログリッドといった、具体的なビジネスモデルも提示していただけたことで、事業展開のビジョンも描きやすくなったのではないでしょうか。
2050年に向けてますます加速していくであろうカーボンニュートラル関連事業を、見逃さずにチェックしていきたいですね。
(対談/佐藤 直人)