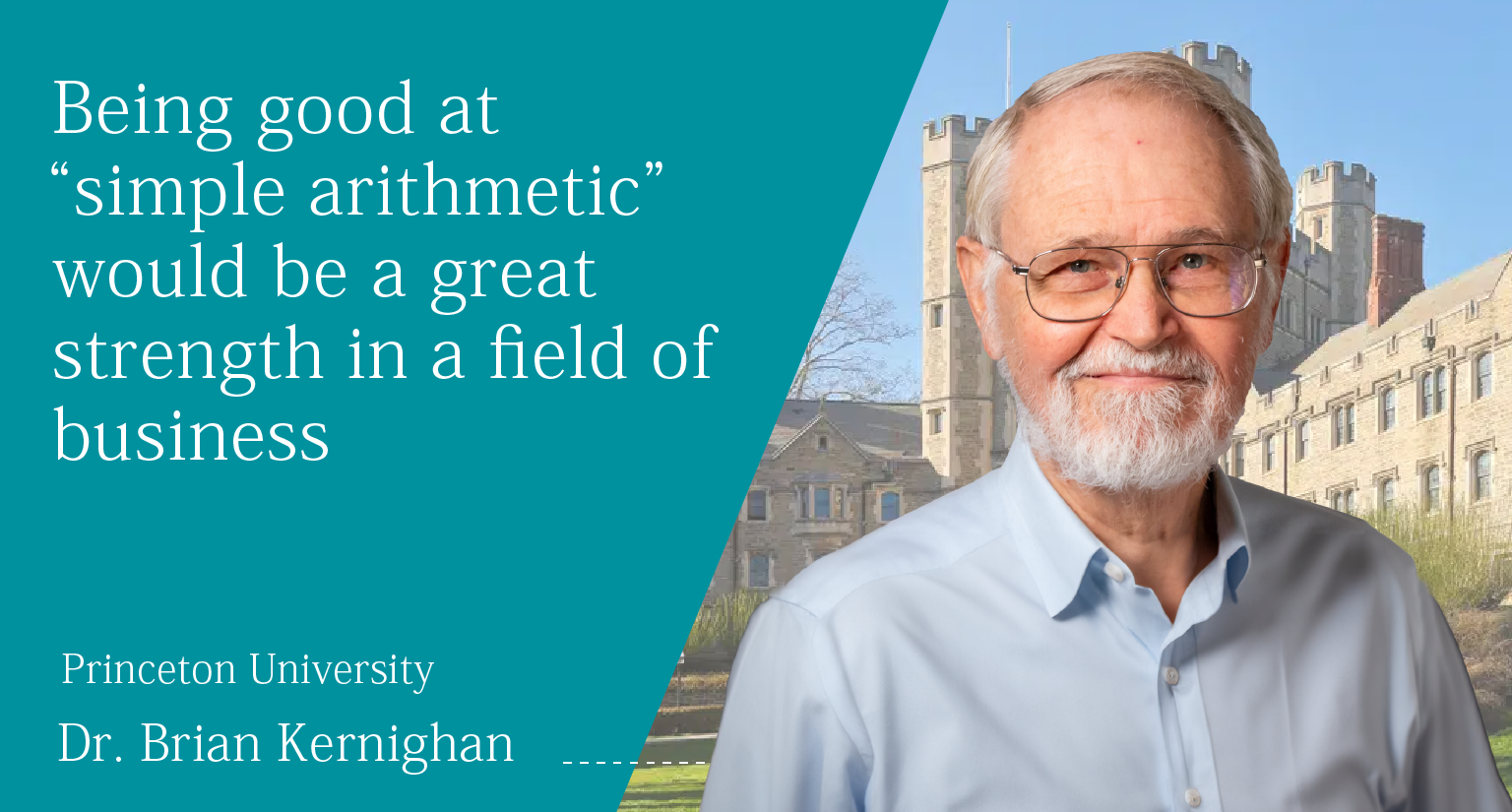ご執筆いただいた方
明星大学 経済学部教授
中田 勇人(なかた はやと)
明星大学経済学部専任講師、准教授を経て、2020年より同大学経済学部教授。この間、早稲田大学政治経済学部非常勤講師、トロント大学訪問研究員を歴任。
専門は国際金融に関する実証分析で、特に近年では石油価格の変動がマクロ経済や株式市場に与える影響を研究。
主な著書に『国際金融論15講』(共著、新世社)などがある。
以下の図(図1)は2022年初頭から直近(2023年3月前半)までの円ドル為替相場の推移である。2022年初めに1ドル115円前後だった円ドル相場は円安ドル高が進行し、10月には1ドル150円に達した。その後、1ドル130円台まで円高ドル安方向に戻したものの、依然として2022年初頭よりもかなりの円安が進んだ水準にある。

※図1:日本銀行のデータを元に筆者作成
2023年の為替レートはどのように展開するのだろうか。筆者は国際金融の研究者であり、トレーダーや市場関係者のような予測は不可能なので、近年の経済学の議論や過去のエピソードから、今後のヒントになるものがないか考えてみたい。
現在の外国為替市場の取引の大半は貿易取引などの実需ではなく、金融取引に基づいている。そのため、経済学では主に金融変数、特に金利が為替レートを決めていると考えている(ただし、後で述べるように長期的には別の要因も重要となる)。金利水準に大きな影響を与えるのが各国の中央銀行の金融政策である。例えば、2008年のリーマン・ショック後に日本の除く主要国の中央銀行が一斉に金融緩和に踏み切ったため、急激な円高が生じたことはよく知られている。
円ドル相場を決まるときは日米の金利が関係する訳だが、円ドル相場を決定する上で最も重要な要因はアメリカの中央銀行であるFED(連邦準備制度)の金融政策、特に政策金利であるフェデラル・ファンド金利(FF金利)の動向とされる。
図2では、2022年初頭から直近までのFF金利の推移を示しているが、2022年1月のゼロに近い水準(0.08%)から、たび重なる利上げによって4%台半ばにまで上昇していることが分かる。金融取引に基づく資金の流れは収益率の高い国に向かうので、ゼロ金利を継続している円に比べドルの価値が上昇する(円高ドル安)のは当然とも言える。
つまり、2023年の為替相場(ここでは円ドル相場)の展開を考えるためには、今後のアメリカの金融政策の動向について考えなければならない。アメリカの金融政策はどのような要因によって決まるのだろうか。近年の世界経済は世界金融危機、コロナ感染拡大と2度の大きなショックに見舞われた。これに対してアメリカを含む各国の中央銀行は、経済の急激な落ち込みやデフレの発生を防ぐため、政策金利をゼロに近づけるだけでなく量的緩和など金利以外の政策手段を積極的に打ち出してきた。しかし、デフレの懸念が遠のくにつれ、日本を除く主要国の金融政策は、再び政策金利の操作を主な手段とするようになっている。
量的緩和以前のアメリカについてはテイラー・ルールという考え方が金融政策の動向(政策金利の動き)を上手く説明していたことが知られている。テイラー・ルールでは政策金利の水準を①インフレ率と目標インフレ率との乖離、②需給ギャップ(需要と潜在的な供給力の差)に依存する形で決める。具体的にはインフレ率が目標インフレ率より高いか、需給ギャップがプラス(需要が潜在的な供給力を上回る)のときに金利を引き上げ(金融引き締め)、逆では金利を引き下げる(金融緩和)というルールである。
FED(連邦準備制度)の目標インフレ率は2%とされているので、2022年の様にインフレ率(前年同月からのCPIの変化率)が7%からピークで9%台に達したのでは、急激な金利の引き上げは避けられないものだったと言える。

※図2:セントルイス連邦準備銀行のデータを元に筆者作成
このアメリカでの急激なインフレをもたらした要因は何だろうか。2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻は資源、食料価格を急騰させ、世界各国のインフレを悪化させたさせたことは間違いないと思われる。しかし、東京大学の渡辺努教授は各国での物価上昇はウクライナ侵攻前から始まっており、根本的な要因は別に探すべきとしている(渡辺努(2022)『世界インフレの謎』講談社現代新書)。
渡辺教授がアメリカのインフレの主な要因と見ているのは「パンデミックの後遺症」である。2020年に始まったコロナ(COVID-19)の感染拡大によって、都市のロックダウンや外出の自粛によって各国の経済活動は大きな影響を受けた。まず、外出が必要なサービス消費は減少し、自宅で消費できるモノの需要が拡大した。また、中心に外で働くことを控える人が増え労働力が減少した。一方で、パンデミックは世界的なサプライチェーンにも影響を与え生産活動が停滞した。これらの要因から財の需要と供給のバランスが崩れたこと(供給不足)が、アメリカのインフレの主要な要因と考えられているのである。
しかし、アメリカではパンデミックがある程度収束し、社会は通常の状態に回帰しているように見える。このインフレも終息に向かっているのだろうか。渡辺教授も、パンデミックをきっかけとしたインフレは、新しい価格体系への調整なので、いずれ終了すると見ている。それでは、この新しい価格体系と為替レートの関係はどう考えればよいのだろうか。
経済学で長期的な為替レートの水準を決めると考えられているのは両国の物価水準である。この長期的な為替レートの水準を「購買力平価」と呼ぶが、両国の財の価格が為替レートで換算すると等しくなる水準と考えられている。購買力平価の考え方を特定の商品(マクドナルドのビッグマック)に応用した、「ビッグマック指数」について知っている方も多いだろう。
現在、日本の物価水準も上昇を続けており我々の生活にも大きな影響を与えているが、インフレ率の高さは欧米諸国と比べると低い水準にとどまっている。この傾向が続いたままとすると、インフレが落ち着いて日米が新しい価格体系に達したときパンデミック前よりもアメリカの物価水準が日本に比べて高くなっているので、円ドル相場はパンデミック前よりも円高ドル安になっていなければならない。つまり、アメリカのインフレに追いつくような激しいインフレが日本でも起こるか、円高ドル安がどこかで進行するかのどちらかという事になる。
ただし、いつどのようにこの調整が起こるのか予測するのは困難である。このことを考えるために1980年代前半の事例について見てみよう。1980年代前半は現在と同じく、インフレを抑え込むための金利引き上げが、円安ドル高を引き起こした時期である。1980年代初頭は第2次石油ショックの発生などでインフレ率が年10%以上に達していたが、1979年に就任したボルカーFRB(連邦制度準備理事会)議長はマネーの縮小によるインフレ率の抑え込みを図りFF金利は急激に上昇した。これに伴って、1983年にはインフレ率も5%以下にまで低下させることができた。
一方、同時期の円ドル相場を見るとそれまで円高ドル安方向に動いていたのが、アメリカの金融引き締め、金利上昇によって円安ドル高に転じた。これは予想の範囲内であったが、アメリカのインフレが落ち着き、FF金利が低下し始めても円高ドル安が数年にわたって続いたのである。これは予想されない展開だったため、1980年代前半には円ドル相場の動きは経済のファンダメンタルズ(基礎的条件)と無関係な「バブル」ではないかという議論も行われた。いわゆる日本の「バブル経済」は1980年代後半の現象なので、それに先駆けた議論であった。
しかし、多くの読者がご存じの通り、1985年のプラザ合意をきっかけに急激な円高ドル安が進むことになった。このとき実現した円ドル相場は1980年代初頭よりも円高ドル安水準であった。1980年代前半、日本銀行はアメリカに比べインフレ率を低位に抑えることに成功していたので、1980年代初頭よりも円が高い水準に増価したのは購買力平価の考え方と整合的と言えるだろう。1980年代の経験は、高インフレというショックに見舞われたとき、ショックが収まっても為替レートが速やかに長期的な水準に調整されるとは限らないことを示している。
本稿の考察は、現在のように世界経済が大きなショックに見舞われているとき、中長期的な為替レートの見通しが非常に難しいことを示しているが、本稿の内容が為替相場の動きを考える上で何らかのヒントになれば幸いである。