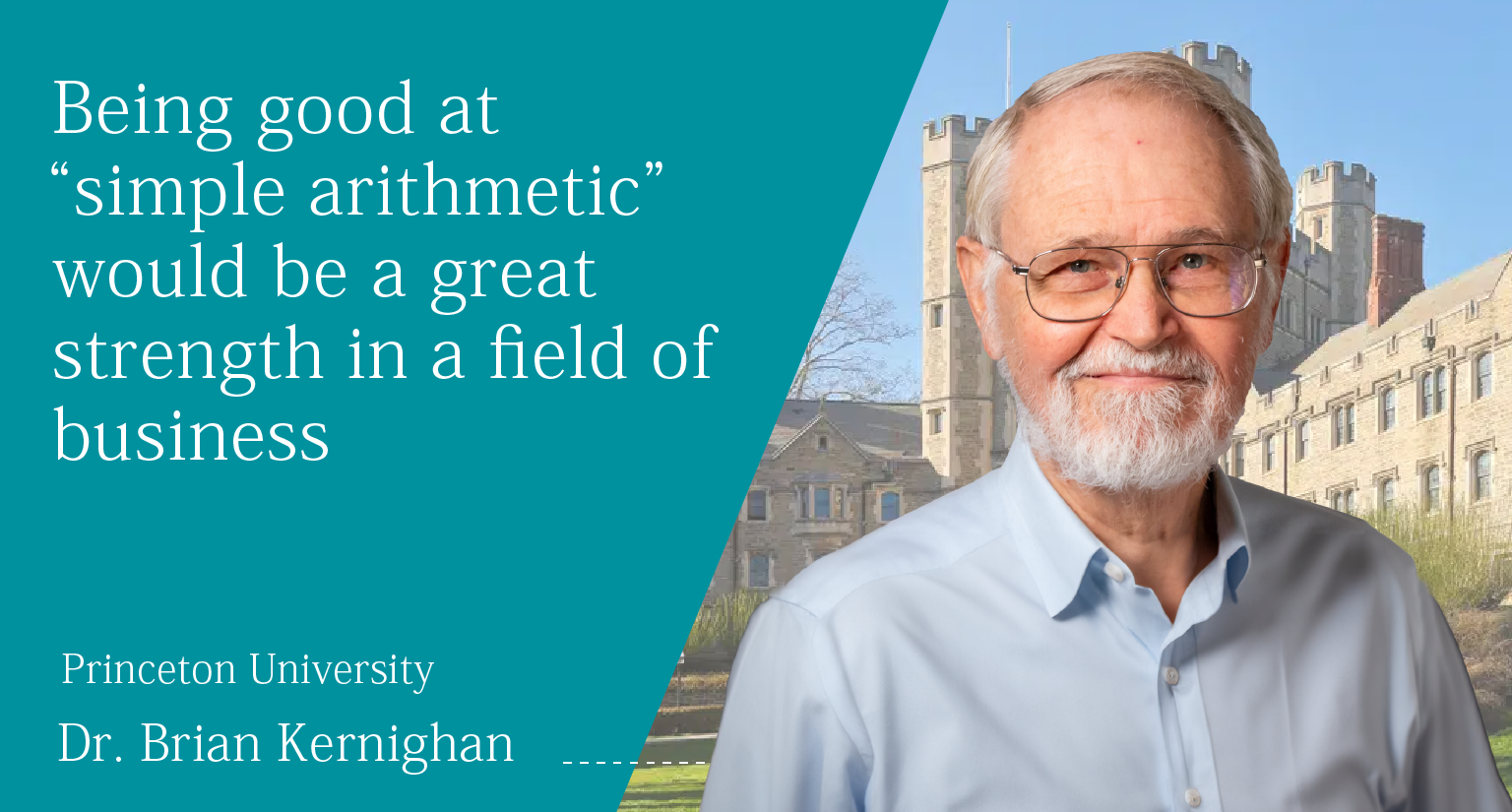「創造力」とは、小さいうちに経験した遊びや生活経験によって育まれる思考能力とされています。この思考能力はあらゆる問題を解決する上で非常に有効であるため、どのような仕事においても大きな成果を生み出す源泉と言えるでしょう。
かつての日本には、自らの手を動かし試行錯誤して楽しみながらオリジナルのものを作る、まさに創造性を育む環境がありました。しかし、現代の日本ではそのような環境は極端に減ってきており、GAFAなどの革新的企業を生み出し続ける米国などとの差は広がるばかりです。
今後の日本において子供の創造性を育む場を再構築・進化させていくためには、どのような教育活動を行い、そして支援環境などを整える必要があるのか。そこで今回、子供が自ら主体的に取り組むことで養われる創造性を育む場づくりに、より豊かで先進的なアプローチで取り組まれてきた、慶應義塾大学の石戸奈々子先生にインタビューさせていただきました。

取材にご協力頂いた方
慶應義塾大学 大学院メディアデザイン研究科 教授
石戸 奈々子(いしど ななこ)
東京大学工学部卒業後、マサチューセッツ工科大学メディアラボ客員研究員を経て、NPO法人CANVAS、株式会社デジタルえほん、一般社団法人超教育協会等を設立、代表に就任。総務省情報通信審議会委員など省庁の委員やNHK中央放送番組審議会委員を歴任。デジタルサイネージコンソーシアム理事等を兼任。政策・メディア博士。
著書には「子どもの創造力スイッチ!」「賢い子はスマホで何をしているのか」「日本のオンライン教育最前線──アフターコロナの学びを考える」「プログラミング教育ってなに?親が知りたい45のギモン」「デジタル教育宣言」をはじめ、監修としても「マンガでなるほど! 親子で学ぶ プログラミング教育」など多数。これまでに開催したワークショップは 3000回、約60万人の子どもたちが参加。実行委員長をつとめる子ども創作活動の博覧会「ワークショップコレクション」は、2日間で10万人を動員する。デジタルえほん作家&一児の母としても奮闘中。
創造力は多様な価値観が混在した環境で生まれる
佐藤:石戸先生は現在様々な活動をされていますが、始められたのはどんなことがきっかけだったのでしょうか?
石戸教授:よく多くの方から「色々なことをやっているんですね」と言われるのですが、私はこれまで一貫して「クリエイティブな場づくり」という一つのテーマに取り組んできました。特に注力してきたのは「子供たちの創造的な学びの場づくり」で、これを産官学連携で取り組んでいくことに長年尽力してきました。その過程で必要に応じて新しい組織を立ち上げたり、声がかかるポジションや仕事があったり。ネットでソーシャルにつながって、時間的、地理的制約を超えた様々な人たちと協同で、横断的に取り組んできました。
佐藤:なるほど。学生時代からそういったことにご興味をお持ちだったんですか?
石戸教授:いえ、幼少期からずっと宇宙に関わる仕事をしたいと思っていたので、航空宇宙工学が学びたいと考え、大学を選択し、工学部に入学したんです。
しかし、授業でたまたまボストンにある「MITメディアラボ」の話を聞いた時、その存在に強く惹かれたんです。10年以上にわたり宇宙関連の仕事に就きたいとこだわっていたのですが、「メディアラボ」に出会った瞬間に、私が行くのは宇宙ではなく「メディアラボ」だと感じました。宇宙に対する憧れも、「メディアラボ」への共鳴も、未知なものに対する私の好奇心の表れだったと思います。しかし、宇宙は今ある世界の探求であるのに対し、同じ「未知の世界」でもメディアラボというのは、デジタルの未来社会を想定した世界、それはつまり「自分達で何も無いところから創造して形にしていくデジタルの世界」です。未知であれ、既存の世界である宇宙よりも、「今はまだ無い世界を自分たちの手で創っていく」メディアラボのような世界を作ることの方により強く惹かれました。
佐藤:幼い頃からの夢が一瞬で変わってしまうほど、とても衝撃だったのですね。そう聞くと私もとても興味を惹かれますが、メディアラボとはどんなところなのでしょうか?
石戸教授:メディアラボに実際に足を運んでみると、そこには理想的な学びの場、創造の源泉がありました。オープン性とデザイン性を備えた空間で、まるでひらめいたらすぐに作ることができるおもちゃ箱のような環境でした。そして、そこにいる人達は性別も年齢も出身も専門分野も多種多様で、かつそれぞれが世界一を誇る深い専門性を持っている斬新で刺激的なコミュニティを形成していたんです。さらに、学生も教授も、それに世界中から集まるスポンサー企業も夜通し議論し、連携して取り組む平等な関係性が築かれているのも魅力的でした。
常に非常識なことに挑戦し、新しい価値を創りだすことに最大限の賛美が集まり、社会との接点の中で研究を進めていく研究スタイルがそこにありました。イノベーションの源泉は、こういう場から生まれていくのだと衝撃を受けたんです。そして「私もメディアラボのようなワクワクした学びの場を日本でも創りたい」と思ったのが、全ての活動のきっかけです。
デジタル技術を加えたイベントによって学びをより豊かに創造性の高いものへ
佐藤:メディアラボでのご経験が全てのご活動の起源だったのですね。その実現に向けて現在まで、CANVAS、デジタル教科書、プログラミング教育の必修化、デジタルえほん、超教育といった多くの活動に取り組まれてこられたと思いますが、まず最初に立ち上げられたというNPO法人「CANVAS」についてお聞きしてもよろしいでしょうか?
石戸教授:はい。最初にCANVASという組織を立ち上げ、子どもたちの創造的な学びの場を産官学連携で推進する場をつくりました。これからの時代に必要な学び、それはつくりながら学ぶ学びであり、遊びと学びの秘密基地であり、主体的で協同的で創造的な学びを、開発・普及していきたいという想いからです。そしてそのような新しい学びをファッションショーのようにポップにたのしく伝えたいと思って、毎年ワークショップコレクションというワークショップの博覧会イベントを企画・実施してきました。造形、音楽、電子工作、ダンス、デジタルなど分野はさまざまですが、すべて「つくる」ということを大事にしたワークショップの博覧会イベントです。
佐藤:なんだかとても楽しそうですが、具体的にはどういったワークショップがあるのでしょうか?
石戸教授:例えばプログラミングでデジタルものづくりをしたり、自分で楽器をつくって音を奏でたり、粘土で映像をつくったり様々です。一人ひとり好きなこと、得意なことが違うと思います。しかし、ワークショップコレクションに来れば150個の多様な創造活動がある。どれか1つでも2つでも自分の好きなものに出会えるとよいなと願っています。というのも、CANVASは「子供達が遊びながら夢中になっている時にこそ最も最高の学びが生まれる」と考えているためです。開始当初の来場者は500人でしたが、150のワークショップが一堂に会して二日で10万人以上の子供たちが来てくれる企画に成長しました。さらには、仙台、京都、山口、福岡など全国各地に展開しています。
ワークショップでは、子どもたちが「みんなで何かを創る」ことを大切にしていますが、ワークショップコレクション自体も、みんなで創ることを大切にしています。学校の先生、大学関係者、ミュージアム関係者、アーティスト、各種研究者 ・技術者、様々な企業、行政関係者、学生、お父さん、お母さん、 おじいちゃん、おばあちやん。そして主役の子どもたち。出展者も来場者も、約1000名のボランテイ ア・スタッフも、みんなで1つの空間をつくり上げてきました。
佐藤:子どもの創造力を育む場としてはとても大規模、かつ子供たち一人一人がワクワクして好奇心を持って取り組める素敵なイベントですね。
産官学などあらゆる機関を巻き込む活動ならNPO法人
佐藤:ちなみに「CANVAS」をNPO法人にされたのは何か理由があったのですか?
石戸教授:産官学含めたあらゆる組織・人と連携をしながら、未来の子供たちの学びの場を作っていく取り組みをしたかったからです。「世界中の多様な価値観の人と協働して新しい価値を創っていく力」、言葉を替えるならば、コンピューターに代替できない力である創造力とコミュニケーション力がこれからの子どもたちには必要だと考えています。そのためにも、知識の記憶暗記型の学びから思考創造型の学びに変えていかなければいけないし、それを学校や家庭だけに任せるのではなく、ありとあらゆる大人が手を取り合って実現する必要があると考えたのです。
とはいえ、NPOの活動を始めたばかりの頃は活動の主旨があまり分かってもらえず、主に学校外での活動がメインでした。そこで私たちが実現したい学びのスタイルを楽しく分かりやすく広げるためにはどうすればいいか?と考えた末に始めたのが、先ほどのワークショップコレクションという博覧会イベントなんです。
佐藤:なるほど。教育の世界で活動範囲を広げるには、NPO法人として取り組むことは将来的に学校などの公的機関と連携しやすいという利点があるんですね。
石戸教授:その他にも、大学でサマーキャンプ(※)も展開してきました。2003年に始めた当時は、大学キャンパス内でのデジタルサマーキャンプは日本初の取り組みであったはずです。アメリカで、ハーバード大学、スタンフオード大学、MITなど、世界に名だたる大学のキャンパスが夏休みにキャンパスを子どもたちに開放している姿勢に感銘を受けました。日本でもそういう文化をつくれないか?と考えはじめました。また、地域の子どもたちが地域の情報を様々なメディアを活用して発信する活動もしてきました。常に気をつけていたのは、各地域で自律分散的にこのような活動が持続的に推進されるコミュニティーづくりです。こうして学校外で様々な取り組みをしてきたことで、CANVASの活動が徐々に認知されてきたんです。
※サマーキャンプ:夏休みに行う野外活動を通じた体験学習。アメリカが発祥とされる。
ただ、NPOの活動を始めて8年ぐらいたった頃にふと考えてみたら、私たちがCANVASの学びを届けられた子供の数は50万人だったんです。50万人しか届けられていなかった。でも、日本には小中学生が1000万人いるんですよね。すべての子供達に新しい学びの環境を届けたいと考えた時にどうすればいいかと考えると、やはり学校での環境整備が必要ではないかと改めて痛感しました。そこで、子どもたちの学びを強化する手段として、1人1台情報端末を整備する運動、デジタル教科書の導入やプログラミング教育の必修化への働きかけをはじめました。思考・創造型の学びへ変化するためです。
新教育システム導入の障壁だった法律を変えるということ
佐藤:なるほど。そうした流れから、デジタル教科書やプログラミング教育の普及活動へも取り組まれていかれたんですね。
石戸教授:そうです。プログラミングは2002年設立当時から取り組んでいましたし、1人1台環境整備はデジタルランドセル構想として2005年に発表しましたけれど、実際に本格的にそれに向けて活動をはじめたのは2010年頃です。2010年には1人1台構想を実現するためにデジタル教科書推進運動として新たな団体をつくりました。そして、同じ年に、日本政府は2020年までに一人1台情報端末を持って学習する環境を整える方針を示してくれました。しかし、この運動は、とにかく政治家、企業、学界さまざまなところから大きな反対があり、とても大変でした。デジタル教科書を実現するための法改正を求め、与野党超党派からなる議員連盟を作っていただき、教育情報化を推進する基本法を作り、そこに予算がついて本格導入されたのは2020年と時間がかかってしまったのですが。コロナというある種、外圧が後押しとなって場面転換を迎えた側面もあるので、それがなければもっと時間がかかっていました。
プログラミングも同様で、同じ頃、諸外国のプログラミング教育必修化の流れを受けて、そろそろ日本でも実現が可能なのではないかと、プログラミング教育を推進するPEGというプロジェクトを立ち上げ、本格的に活動をはじめました。必修化を目指し、1年で2万5千人の子どもたちにプログラミング教育を届け、1000人の先生方に研修し、13地域でコミュニティを形成して展開し、モデルケースをつくるとともにそのノウハウを提供してきました。プロジェクトスタート時には、googleのエリック・シュミット会長にお越しいただくなど、たくさんの支援を頂きました。
佐藤:法律を変えるということは、やはり相当大変なことなんですね。
石戸教授:そうですね。活動をはじめて20年が経ちます。ワークショップは至る所で開催されるようになり、デジタル教科書等に関する法制度の整備、プログラミング教育の必修化、それらを含む教育情報化推進法の成立、1人1台環境の整備。これまで提案してきたことがほとんど実現したことは嬉しく思います。
創造力を育むための新たな総合芸術という取り組み
佐藤:ちなみに、長きにわたりデジタル教育の推進活動運動を行われていた中で、何かご自身で感じられていたことなどはあったのでしょうか?
石戸教授:公教育の中での子供たちの学習環境を整える一方で、それが実現した時には、子供たちにとって良質なコンテンツが開発・普及する環境も整備したいなと考えていました。そこで、デジタルえほんの活動もはじめました。ここでは、子供たちのための今までにない表現様式やコミュニケーションを生み出す「道具」として「デジタルのえほん」を広めることをテーマとしています。想像力 ・創造力を育み、子どもたちを魅了し、夢中にさせる、親も一緒に楽しむ、そんな新しいデジタル表現の開拓を目指してきました。そしてその普及のためにデジタルえほんアワードや国際デジタルえほんフェアも開催し、いまでは世界52カ国から参加があります。
子供だけでなく全ての人が参加できる共創の場を作っていく
佐藤:なるほど。大人も子供も関係なく創造性を発揮できる素晴らしい取り組みですね。さらに現在は「超教育協会」や「B Lab」といった組織の始動に尽力されてらっしゃるとお見受けしたのですが、この新たな2つの組織の立ち上げにはどういった経緯があったのでしょうか?
石戸教授:先程申し上げたように、教科書に関する法制度も整備され、加えてプログラミング教育も必修化されたことで教育情報化推進法も成立し、子どもに一人一台端末という情報環境も整備された。しかし、それは社会への、世界の教育へのキャッチアップにすぎないと考えています。それだけではなく今の時代にふさわしい最先端の教育を構築したいと考えました。そこで2018年に31の業界団体とともに超教育協会という団体をつくり、教育をリデザインするとりくみ、全ての学習者を主体とした、従来の学校の枠を取り払った学びの場「超教育」を構想する試みをはじめました。
それが超教育協会という団体です。具体的には、教育・人材育成に関する社会提案・政策提言、未就学児から社会人まで立場の枠を超えた未来の学習環境のデザイン、AI/IoT/ビッグデータ/VR・AR/ブロックチェーン等先端技術の教育への導入策の検討、ICT教育の推進、EdTechビジネス支援、ICT・AI・IoTプロフェッショナルの育成・確保等を行っています。AIやブロックチェーンなどSociety5.0を代表する技術は、教科、試験、学校など、学びの内容・環境・評価を問い直す変化をもたらす可能性があります。教科面ではAIが教科を横断する超個別学習を実現するでしょう。そのためのカリキュラム再編成も求められます。それは検定や学習指導要領の内容や存在を問うことになり得ます。また、ブロックチェーンで学習履歴を全て蓄積することで、試験をする必要がなくなるでしょう。入試のあり方を問うことになります。そうした変化により、学年や学校など教育機関の枠を超える学習環境をデザインすることができるようになるでしょう。学校制度のあり方自体も問うことになり得ます。
そんな変化をおこしてくれるのが超教育であり、そしてそれはアフターコロナ教育だと考えています。
高等教育もしかりです。コロナ禍ですべてオンライン対応。キャンパスに行く必要がまったくなくなりました。対面・リアル講義前提で組み立てられてきた各種規制を一度すべて廃止し、オンライン・デジタル前提の制度につくりなおす必要があると思います。いまの現状にしっかりと向き合わないと、学習者自身が学習データを保有しつつ、超個別最適化された、分散化された学習環境が実現できたら、個別大学はいらなくなるかもしれない。技術はツールにすぎないとよく言われますし、そのとおりだと思いますが、技術の進展とともに教育も変化してきたという歴史もあります。活版印刷の発明は教科書を生み出し、一斉授業という教育手法を確立した。20世紀には映画、ラジオ、テレビなどの新メディアが教育に利用された。21世紀、ITやAIは社会が求める人材像を変え、それがまた教育を刷新する。それがどういう教育なのか。考え、実装してみたいと考えています。
そして、大学は教育だけではなく、研究も大きな軸ですが、ちょっと先のおもしろい未来をみんなでつくる新しいラボをつくりたいと考え設立したのがB Labです。MITメディアラボに足を踏み入れたときから、いつかラボをつくりたいと思っていたのですが、ようやく着手しはじめました。Beyond(ビヨンド)、Borderless(ボーダーレス)、Breakthrough(ブレイクスルー)の頭文字をとった「B Lab」は、世界の大学・研究所、企業、地域、行政、個人、ありとあらゆる垣根、枠組みを超えて、ありとあらゆる組織や個人と連携しておもしろい未来をみんなで共創する参加型プラットフォームです。個人も企業も行政も地域もみな繋がり、課題、アイディア、技術、お金、スキル、人をマッチングさせ、小さな創造から大きな創造までおもしろい未来をみんなでつくることを目指しています。既に国内外問わず様々な拠点ができて、現在様々なプロジェクトが生まれています。
佐藤:なるほど。子供だけでなく全ての人達を対象にして、更に進んだ教育を目指している壮大な事業なのですね。例えば、このB Labという団体では具体的に今どういったことをされているんですか?
石戸教授:一つには、理化学研究所の革新知能統合研究センターと共同研究で「超校歌~AIがつくるみんなの校歌~」というプロジェクトがあります。日本特有の学校文化の一つである校歌ですが、その起源は明治政府の教育改革の一環として価値観や思想の統一のために導入されたと言われていて、その後「郷土の歌」として広がったものなんですよね。令和の時代に私たちが選ぶ校歌とはどんなものであるか、AI技術を用いてそれに相応しい校歌を作ろうという、そういったプロジェクトです。
その他には、若年層のソーシャルアクションを後押しするような超SDGsという取り組み、大学の枠を超えてスタートアップを支援する超起業学校プロジェクトなども動いています。年に1回は「ちょっと先のおもしろい未来(Change Tomorrow。通称:ちょもろー)」というイベントも実施しています。
佐藤:先ほどの先生のお話にあった「おもしろい未来」を創っていく、ということをすごく実感できる活動ですね。最後に、今後石戸先生が目指されているところをお聞きしてもよろしいでしょうか?
石戸教授:そうですね。私はMITメディアラボに行った時、「デジタルの未来社会を描くビジョン」、これを形にするための「産官学の主要プレーヤーを集める求心力」、そして「ビジョンを社会実装するパワフルな行動力」といった、その場の全てに強烈に惹かれました。ですので、私はそうした沢山の人々が様々な物を生み出す「場」や「プラットフォーム」を作りたいと思っています。なぜなら、今、新たな技術的・社会的変化の岐路に立っていると思うからです。だからこそ、このタイミングで国内外の研究機関の企業も行政もありとあらゆる組織、人を繋いで、世界中をフィールドにして新しい社会を作っていく「場」が必要だと考えています。自立分散協調。ソーシャルで、オープンで、参加型で。様々な人たちの治験や得意技を融合させることで、新しい技術、サービス、コンテンツ、ビジネス、社会を生んでいくプラットフォーム、増殖炉をつくっていきたい。
そのような「場」として私は「B Lab」を成長させていきたいと考えていますが、ここで作ることというのは必ずしもノーベル賞を取るような大それたことではありません。新しいビジネスの創出といった大きな創造だけでなく、日常生活のちょっとした工夫や発明などの小さな創造まで、全てが私たちの研究範囲です。規模の大小問わず、皆が面白い未来を思い描き、新しい社会創造に全ての人が主体的に参画する場をつくりたい。一人ひとりが生涯にわたり、探究心を忘れず、社会創造の一員となる。「B Lab」はイノベーションとインキュベーション、i2(あいじじょう。あいスクエア)を推し進める場であり、コミュニティであり、ネットワークなのです。
まとめ
今回は、慶應義塾大学の石戸奈々子先生にお話を伺いました。
人口減少によりGDP低下が続く日本の未来を救うには、これから生まれてくる子供たちの創造性をより豊かに進化させていく環境こそが必要です。石戸先生が構築を試みるMITメディアラボのような「場」こそが、その理想形と言えるでしょう。
確かに、教育に関わる活動を推進していくためには、法制度改革など長期に及ぶ地道な活動を避けて通れません。ですが、そのような障壁さえも超えてきた石戸先生のこれからの取り組みは、今最も注目すべき社会活動の一つと言えるのではないでしょうか。
(対談/佐藤 直人、執筆・編集/佐藤 優)